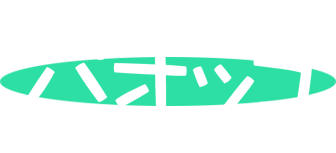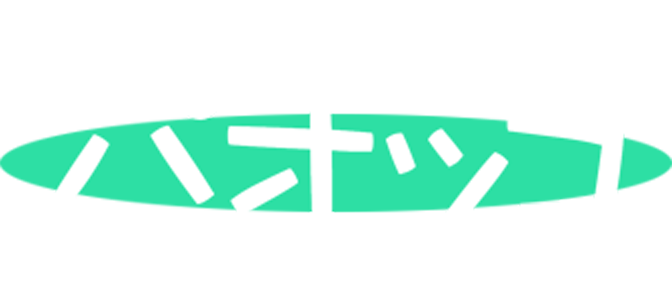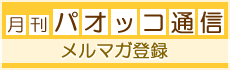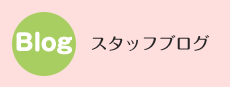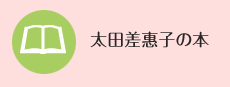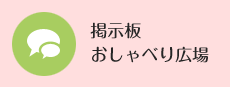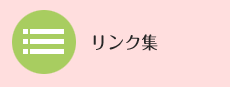遠距離介護の体験談
パオッコに寄せられたたくさんの遠距離介護の体験談。誰かの体験が他の誰かの役に立つように、貴重な体験談を集めました。あなたの体験談も是非お寄せ下さい。投稿の方法はこちら
故郷を離れて生活しているうちに、いつのまにか老いていく親。心配ではありますが、だからといって故郷にUターンするにも親を自分たちのもとに呼び寄せるにも、さまざまな困難があります。残された方法として、親子が別々の土地で暮らし続け、子は遠くから親のケアに心を砕く「遠距離介護」……この方法を選択するにあたって、子世代にはどんな思いがあるのでしょうか。投げかけた5つの質問に答えていただく形で体験談をお寄せいただきました。
![]() 郷里のご家族の状況…親ごさんのお住まいの地域、年齢やひとり暮らしかどうかなど
郷里のご家族の状況…親ごさんのお住まいの地域、年齢やひとり暮らしかどうかなど
![]() 遠距離介護を選択された理由
遠距離介護を選択された理由
![]() 現在(もしくは過去)、どういうかたちで親ごさんのケアをなさってますか?
現在(もしくは過去)、どういうかたちで親ごさんのケアをなさってますか?
…帰省の頻度、介護保険を使っているか、民間の各種サービスを利用など
![]() 遠距離介護で苦労なさっていること、もしくは不安に思うことなど
遠距離介護で苦労なさっていること、もしくは不安に思うことなど
![]() その他…親とはなれて暮らす子どもの言いぶんなど
その他…親とはなれて暮らす子どもの言いぶんなど
体験談:015
H・Nさん (岐阜県在住 50代女性)
![]() 遠距離介護生活の始まりは平成8年。埼玉県在住の父が胃癌とわかり手術の日程を決めるころから母がうつ病に。父の入院直前に母の状態が悪化し、精神科の専門病院に入院させることとなった(閉鎖病棟)。両親は東京都のそれぞれ別の病院に入院することになり、岐阜県から泊まりで行くことに(両親が住んでいたマンションにしばらく滞在)。その頃、私のお腹には9ケ月になる次男がおり、大きなおなかを抱え、片手に二歳の長男の手を引き、片手にベビーカーを持ち両親それぞれが入院する病院に毎日 電車で通うという生活で大変な日々だった。 父の胃癌の手術は成功し、その後の経過も順調だったが、母のうつは次第に悪化。父一人では介護しきれなくなり、介護サービスを入れたり、私も幼い二人の子を連れ岐阜から埼玉に頻繁に通うようになった。
10年間の遠距離介護中は母の行動で警察から連絡が来たり、二人してけがをして救急病院から「すぐ来てください」と連絡が来たり…一日も気が休まらない日々が続いた。父もがんばって母の介護をしていたが、胃癌、大腸がん、リウマチ、一過性脳虚血発作等でだんだんと体も弱り、母を見送ったあとはとても一人にはしておけない状況で岐阜に呼び寄せ同居が始まった。いろいろあり、家族も大変だったが6年の介護の末 見送ることができた。
遠距離介護生活の始まりは平成8年。埼玉県在住の父が胃癌とわかり手術の日程を決めるころから母がうつ病に。父の入院直前に母の状態が悪化し、精神科の専門病院に入院させることとなった(閉鎖病棟)。両親は東京都のそれぞれ別の病院に入院することになり、岐阜県から泊まりで行くことに(両親が住んでいたマンションにしばらく滞在)。その頃、私のお腹には9ケ月になる次男がおり、大きなおなかを抱え、片手に二歳の長男の手を引き、片手にベビーカーを持ち両親それぞれが入院する病院に毎日 電車で通うという生活で大変な日々だった。 父の胃癌の手術は成功し、その後の経過も順調だったが、母のうつは次第に悪化。父一人では介護しきれなくなり、介護サービスを入れたり、私も幼い二人の子を連れ岐阜から埼玉に頻繁に通うようになった。
10年間の遠距離介護中は母の行動で警察から連絡が来たり、二人してけがをして救急病院から「すぐ来てください」と連絡が来たり…一日も気が休まらない日々が続いた。父もがんばって母の介護をしていたが、胃癌、大腸がん、リウマチ、一過性脳虚血発作等でだんだんと体も弱り、母を見送ったあとはとても一人にはしておけない状況で岐阜に呼び寄せ同居が始まった。いろいろあり、家族も大変だったが6年の介護の末 見送ることができた。
![]() 私には兄がいるが、両親と兄は折り合いが悪く、介護するのは私しかいないと岐阜から埼玉に通った。
私には兄がいるが、両親と兄は折り合いが悪く、介護するのは私しかいないと岐阜から埼玉に通った。
![]() 遠距離介護中は、訪問介護を週三回利用。調理や掃除をお願いした。母は調子が良い時はデイサービスにも通い、なるべく父が休める時間を作った。両親が住んでいるところの隣の市に親戚がおり、何かとお世話になった。月一回(遠距離介護の終盤は毎週末)帰省する際には、隣家の方にお土産を持って行ったり、ケアマネージャーや民生委員さんのところに行ったり、マンションの管理人や日頃お世話になっているたくさんの方々のところに顔をだし、日頃のお礼と見守りのお願いをしに行った。
遠距離介護中は、訪問介護を週三回利用。調理や掃除をお願いした。母は調子が良い時はデイサービスにも通い、なるべく父が休める時間を作った。両親が住んでいるところの隣の市に親戚がおり、何かとお世話になった。月一回(遠距離介護の終盤は毎週末)帰省する際には、隣家の方にお土産を持って行ったり、ケアマネージャーや民生委員さんのところに行ったり、マンションの管理人や日頃お世話になっているたくさんの方々のところに顔をだし、日頃のお礼と見守りのお願いをしに行った。
![]() 緊急のことで行かなくてはならなくても、岐阜から埼玉へは5時間以上かかるのですぐにはかけつけられず、その間に対応してくれる人をさがすのが大変だった。いつ電話がかかって呼びだされるのかと思うと気が気ではなく、心が休まらなかった。母は病気の影響で気分の浮き沈みが激しく、電話で「すぐ来て!」と言われて新幹線に飛び乗り駆けつけると、連れて行った子供の声がうるさいと言われ「子供の声が頭に響くからもう帰って」と言われたことも。 育児と介護が重なり大変だった。32歳から始まった介護だが、まわりの友達はまだ子育てが忙しく介護とは無縁の人ばかり。だれにも相談できないということがとても辛かった。
緊急のことで行かなくてはならなくても、岐阜から埼玉へは5時間以上かかるのですぐにはかけつけられず、その間に対応してくれる人をさがすのが大変だった。いつ電話がかかって呼びだされるのかと思うと気が気ではなく、心が休まらなかった。母は病気の影響で気分の浮き沈みが激しく、電話で「すぐ来て!」と言われて新幹線に飛び乗り駆けつけると、連れて行った子供の声がうるさいと言われ「子供の声が頭に響くからもう帰って」と言われたことも。 育児と介護が重なり大変だった。32歳から始まった介護だが、まわりの友達はまだ子育てが忙しく介護とは無縁の人ばかり。だれにも相談できないということがとても辛かった。
![]() 両親の介護をするのは私しかいないと頑張ってきた。幼い子二人を置いて数日家をあけるわけにもいかず、片道5時間以上かけて幼子2人を連れて新幹線に乗り通った。何日も家を空けるので主人に申し訳ない気持ち。主人の両親もあまりよく思っていないのではというちょっと後ろめたいような気持ち。一度 両親のもとに行くと、近所へのおみやげ代等も含め4~5万円かかる。そのお金を主人のお給料から出させてもらう申し訳なさ。介護サービスを利用して少し、安心できるようになってからは私も働き、介護のために帰るときは自分の給料から出せるようになり、少しだけ罪悪感が減った。遠距離介護終盤のころには子供も大きくなっており、主人に預けて 私だけで週末に行くことができた。金曜日、仕事を終えてから夜行バスに乗り 日曜日の夜行バスで帰り月曜の朝から仕事に出たこともあった。まだ、私に体力があったからできたのだろうが…。私なりに精一杯やっていたつもりだったが、両親のところから帰るときには 毎回のように「もっと近くにいてくれたらよかったのに」と言われ 遠くに嫁いだことを「親不幸だったのかな」と悩んだ。
両親の介護をするのは私しかいないと頑張ってきた。幼い子二人を置いて数日家をあけるわけにもいかず、片道5時間以上かけて幼子2人を連れて新幹線に乗り通った。何日も家を空けるので主人に申し訳ない気持ち。主人の両親もあまりよく思っていないのではというちょっと後ろめたいような気持ち。一度 両親のもとに行くと、近所へのおみやげ代等も含め4~5万円かかる。そのお金を主人のお給料から出させてもらう申し訳なさ。介護サービスを利用して少し、安心できるようになってからは私も働き、介護のために帰るときは自分の給料から出せるようになり、少しだけ罪悪感が減った。遠距離介護終盤のころには子供も大きくなっており、主人に預けて 私だけで週末に行くことができた。金曜日、仕事を終えてから夜行バスに乗り 日曜日の夜行バスで帰り月曜の朝から仕事に出たこともあった。まだ、私に体力があったからできたのだろうが…。私なりに精一杯やっていたつもりだったが、両親のところから帰るときには 毎回のように「もっと近くにいてくれたらよかったのに」と言われ 遠くに嫁いだことを「親不幸だったのかな」と悩んだ。
10年間の遠距離介護で、介護のための帰省費用を自分の稼ぎから出すために就いた仕事は介護ヘルパー。両親の介護を常時できないので、身近にいる高齢者の手助けをして自分の気持ちを少し軽くしたかったのかもしれない。母を見送ったあとは、少し余裕ができたので ケアマネージャーに転身した。
長い介護生活は今思うと本当に大変だったけど、得たことも多い。
母のうつ病、のちにアルツハイマーとの診断もあった。
父はがん、リウマチ、一過性脳虚血発作、レビー小体型認知症にもなった。
患者の家族として、何人もの医師、あちこちの病院と関わった。
ヘルパーとなってからはプロとして介護する側の苦悩もあった。
ケアマネージャーとなってからは…
今までの大変だったすべてが糧になった。介護する家族の気持ち
ヘルパーとしての気持ち、
ケアマネージャーの気持ち
がわかる。
今までのことは無駄ではなかったのかなとふと思う。
先日もテレビで若いママさんたちが、育児と介護の両立をがんばっている姿を見た。
老々介護でがんばっている方々もたくさんいる。
どうかどうか がんばりすぎないようにしてください。
介護も大事だけど、自分や自分の家族も大事にしてください。体験した者の実感です。
(原文のとおり2016.1.9掲載)
体験談:014
F・Kさん(スイス在住 50代女性) *自由記述での投稿
![]() つい先日、一人暮らしの老父、89歳が「オレオレ詐欺」の被害に会いました。海外生活の私は、何もできず、どこへ怒りをぶつけたらいいのかもわからないまま、ただただ詐欺グループを恨むだけです。
つい先日、一人暮らしの老父、89歳が「オレオレ詐欺」の被害に会いました。海外生活の私は、何もできず、どこへ怒りをぶつけたらいいのかもわからないまま、ただただ詐欺グループを恨むだけです。
今回、お話したいのは、この詐欺事件での悔しい思いも然る事ながら、大手銀行での老人への対応について皆さんにお知らせしたく、投稿した次第です。
詐欺の内容は、よく警察や自治体の防犯サイトにあるようなマニュアル通りの手口でした。「病院にカバンを忘れた、カバンの中に小切手が、内緒でお金を貸して・・・」特に、一人暮らしの高齢者は、電話で優しく「俺だよ」なんて言われると、親心スイッチが入り、声を聞き分ける能力やその場での判断力など、まったく失ってしまうそうです。
歩行困難な父親は、タクシーを飛ばして銀行へ行きました。
ここからが問題です。これだけ事件が多発しているにも関わらず、銀行の窓口では、大金の使用目的を「リフォーム」という詐欺師からの知恵をそのまま丸呑みで終わりだったそうです。
事件後、友人から、地元密着型の信用金庫などでは、老人が大金を下ろす際は必ず別室へ通し、警察へ通報が決まりだと教えてくれました。それで、何度も事なきを得たそうです。それなら、大手都市銀行は何をしているのでしょうか?
銀行のサイトには、金融犯罪等にご注意ください、と小さく注意されているだけです。もう、携帯電話でATMへの誘導は、過去の話。今では、ATMを操作できない高齢者を狙った受け渡し式の詐欺が8割だという現実。振り込めではなく、受け取り詐欺なのです。
銀行窓口の対応如何によっては、今回の老父の事件も未然に防ぐことができたかもしれないと思うと、腹が立って眠れません。
(原文のとおり 2014.10.15掲載)
![]() *自由記述の投稿です。パオッコからの1~5の質問に答える形ではありません。
*自由記述の投稿です。パオッコからの1~5の質問に答える形ではありません。
![]()
![]()
![]()
体験談:013
M・Kさん(東京都 50代女性)
![]() 06 年に父を、07 年に母を見送りました。通いの介護らしきものが始まったのは、05 年に両親(当時 88 歳、85 歳)が相次いで入院、先に退院した母が、京都市の住宅街にある一戸建ての家でひとり暮らしをすることになったころです。実家とは徒歩数十秒の距離に、長男である私の兄(7歳年上)夫婦が住んでいます。また、両親が家を建てた 40 年ほど前からの積み重ねで、ご近所では親戚より近いほど親密なおつきあいが続いており、皆さんで気をつけてくださいました。
私も3歳年上の夫も京都の出身で、81 年の秋から東京で暮らしています。私がフルタイムの職業についていたころは、なかなか里帰りもできませんでしたが、98 年にその仕事をやめてからは講習会を月に1回東京と京都で持つようになり、必然的に毎月両親の顔を見られるようになりました。もちろん、京都での講習を引き受けた理由の一半はそれです。
06 年に父を、07 年に母を見送りました。通いの介護らしきものが始まったのは、05 年に両親(当時 88 歳、85 歳)が相次いで入院、先に退院した母が、京都市の住宅街にある一戸建ての家でひとり暮らしをすることになったころです。実家とは徒歩数十秒の距離に、長男である私の兄(7歳年上)夫婦が住んでいます。また、両親が家を建てた 40 年ほど前からの積み重ねで、ご近所では親戚より近いほど親密なおつきあいが続いており、皆さんで気をつけてくださいました。
私も3歳年上の夫も京都の出身で、81 年の秋から東京で暮らしています。私がフルタイムの職業についていたころは、なかなか里帰りもできませんでしたが、98 年にその仕事をやめてからは講習会を月に1回東京と京都で持つようになり、必然的に毎月両親の顔を見られるようになりました。もちろん、京都での講習を引き受けた理由の一半はそれです。
![]() つききりで介護するほどの必要はありませんでしたし、私にも東京での生活があり、それを放棄してまでのことを誰よりも親自身が望まないとわかっていました。まだ母が元気だったころ、「いつか体がきかなくなったら」という話をしたことがあります。私が京都に来られるのは月に1回がせいぜいだけれど、母が京都を引き払って東京近郊の施設に入ると、少なくとも毎週は会える、と。「そやなあ、それもええなあ」との返事でしたが、京都に友だちの多い母のこと、結局その可能性を真剣に追求することはありませんでした。
つききりで介護するほどの必要はありませんでしたし、私にも東京での生活があり、それを放棄してまでのことを誰よりも親自身が望まないとわかっていました。まだ母が元気だったころ、「いつか体がきかなくなったら」という話をしたことがあります。私が京都に来られるのは月に1回がせいぜいだけれど、母が京都を引き払って東京近郊の施設に入ると、少なくとも毎週は会える、と。「そやなあ、それもええなあ」との返事でしたが、京都に友だちの多い母のこと、結局その可能性を真剣に追求することはありませんでした。
![]() 毎月決まった日にちに帰省して、一緒に暮らしました。1回の滞在日数は、入院するまでは2~3泊、退院後は1週間。8年前、母が変形性膝関節炎で手術を受けたときに、京都市の補助を申請して、玄関と2階への階段と浴室に手すりをつけてはありましたが、それでも急勾配の階段の上り下りがたいへんですので、寝室を2階から1階へ移動しました。電動で角度が変えられるベッドを介護保険で貸してもらい、トイレの近くの部屋に設置、居間にあったテレビもベッドの傍に移動しました。
6週間もの入院生活は母から気力を奪い、傍目にも消耗が見てとれたので、退院後はヘルパーさんに週2回、掃除と洗濯をお願いしました。母は昔から進歩的な性格でしたので、他人さんに家に入ってもらうことなどに対しての戸惑い、あるいは拒絶反応はまったくありませんでした。これらの手続きは兄の助けを借りつつ、母が自分でやりました。
食事の準備は兄嫁に頼ることになり、昼食と夕食を毎日届けてもらいました。食事の内容は兄夫婦と同じで、使った食器は母が毎回自分で洗って拭いて、兄嫁に返していました。母は体調のいい日には近所のスーパーマーケットに行って、朝食のパンやサラダなどの材料を買い置きしたり、好みのものを少し買ったりもして、自由度は保っていました。これは確実に気持ちの張りにつながっていたと思います。ただ、母の矜持でしょうか、食費や雑費を兄嫁に渡していました。
今でも不思議なのは、そんな母が、私の滞在中は所帯の経費をすべて私に負担させて、「おーきに、かんにんえ」のひとことですませていたことです。私自身に多少の収入があったからこそ、母が喜んでいればそれでよしと思えましたが、そうでなかったら、どこかで気持ちの負担が募ったであろうと考えます。
ひとり暮らしですのでお風呂についても不安で、デイサービスを利用してみましたが、入浴のし方など母の期待に沿わないことがあって、やめました。以後、お風呂はヘルパーさんが来てくださっている昼間に入るようになりました。私がいるときには夜の就寝前に入り、毎月私に足の爪の手入れをしてもらうのが楽しみのようでした。
毎月決まった日にちに帰省して、一緒に暮らしました。1回の滞在日数は、入院するまでは2~3泊、退院後は1週間。8年前、母が変形性膝関節炎で手術を受けたときに、京都市の補助を申請して、玄関と2階への階段と浴室に手すりをつけてはありましたが、それでも急勾配の階段の上り下りがたいへんですので、寝室を2階から1階へ移動しました。電動で角度が変えられるベッドを介護保険で貸してもらい、トイレの近くの部屋に設置、居間にあったテレビもベッドの傍に移動しました。
6週間もの入院生活は母から気力を奪い、傍目にも消耗が見てとれたので、退院後はヘルパーさんに週2回、掃除と洗濯をお願いしました。母は昔から進歩的な性格でしたので、他人さんに家に入ってもらうことなどに対しての戸惑い、あるいは拒絶反応はまったくありませんでした。これらの手続きは兄の助けを借りつつ、母が自分でやりました。
食事の準備は兄嫁に頼ることになり、昼食と夕食を毎日届けてもらいました。食事の内容は兄夫婦と同じで、使った食器は母が毎回自分で洗って拭いて、兄嫁に返していました。母は体調のいい日には近所のスーパーマーケットに行って、朝食のパンやサラダなどの材料を買い置きしたり、好みのものを少し買ったりもして、自由度は保っていました。これは確実に気持ちの張りにつながっていたと思います。ただ、母の矜持でしょうか、食費や雑費を兄嫁に渡していました。
今でも不思議なのは、そんな母が、私の滞在中は所帯の経費をすべて私に負担させて、「おーきに、かんにんえ」のひとことですませていたことです。私自身に多少の収入があったからこそ、母が喜んでいればそれでよしと思えましたが、そうでなかったら、どこかで気持ちの負担が募ったであろうと考えます。
ひとり暮らしですのでお風呂についても不安で、デイサービスを利用してみましたが、入浴のし方など母の期待に沿わないことがあって、やめました。以後、お風呂はヘルパーさんが来てくださっている昼間に入るようになりました。私がいるときには夜の就寝前に入り、毎月私に足の爪の手入れをしてもらうのが楽しみのようでした。
![]() 東京・京都間は新幹線で2時間半とはいえ、駅までの往復を加算すると、やはり片道4時間以上かかりますし、移動だけでも疲れます。帰省前後の準備やあと片づけもあり、月のうち10 日はそれにとられるのがつらかったです。不安だったのは、ひとり暮らしの母が何かで倒れて誰にも気がつかれない状況になること。 1日 1回 夕方に、兄嫁が食事を持って訪れてくれるのと、ご近所が見守ってくださるので、それだけが頼りでした。
想定外で慌てたのは、病院で亡くなった父の納骨を済ませたころから、母がおかしくなったことです。本を読みながら 「何にも頭に入らへん 1」 と怒りだしたり、夜ベッドに入るときに「子どもらのお荷物になってる……」 と泣きはじめたり、唐突に説教を始めたり。それが半年ほども続いたように思います。
このころは毎月京都に帰るのが苦端になりました。若いころはあんなにテキパキしていた母が、と思うと悲 しかった。腹も立ちました。母に腹を立てる自分に対 して腹が立ちました。思えば、兄夫婦は母 と四六時中顔を合わせて暮らすわけではなく、食事を運んでくるときにちょっと世間話をする程度です。母は見療に対 して多少は気が張っているので、妙なことは言わないのだろうと思いますが、実の娘の私には何でもとにかく日にして発散していたのでしょう。ハイハイと聞き流すことができず、真剣に向かってしまう私は消耗して、帰りの新幹線では気持ちと体の疲れから、席に座るとすぐに限っていました。
東京・京都間は新幹線で2時間半とはいえ、駅までの往復を加算すると、やはり片道4時間以上かかりますし、移動だけでも疲れます。帰省前後の準備やあと片づけもあり、月のうち10 日はそれにとられるのがつらかったです。不安だったのは、ひとり暮らしの母が何かで倒れて誰にも気がつかれない状況になること。 1日 1回 夕方に、兄嫁が食事を持って訪れてくれるのと、ご近所が見守ってくださるので、それだけが頼りでした。
想定外で慌てたのは、病院で亡くなった父の納骨を済ませたころから、母がおかしくなったことです。本を読みながら 「何にも頭に入らへん 1」 と怒りだしたり、夜ベッドに入るときに「子どもらのお荷物になってる……」 と泣きはじめたり、唐突に説教を始めたり。それが半年ほども続いたように思います。
このころは毎月京都に帰るのが苦端になりました。若いころはあんなにテキパキしていた母が、と思うと悲 しかった。腹も立ちました。母に腹を立てる自分に対 して腹が立ちました。思えば、兄夫婦は母 と四六時中顔を合わせて暮らすわけではなく、食事を運んでくるときにちょっと世間話をする程度です。母は見療に対 して多少は気が張っているので、妙なことは言わないのだろうと思いますが、実の娘の私には何でもとにかく日にして発散していたのでしょう。ハイハイと聞き流すことができず、真剣に向かってしまう私は消耗して、帰りの新幹線では気持ちと体の疲れから、席に座るとすぐに限っていました。
![]() 私が東京から通うことを、母の近所に住んでいる兄夫婦は「1週間くらい」と軽く考えていて、それについては不満でした。母と実際に一緒にいる時間でいうと、 1週間の私のほうが、別居して毎日20~30分程度の兄夫婦よりはずっとヘビーであることが、ある黄味では母自身にも、なかなか理解されませんでした。
滞在中の私が友だちと出かけ、帰ってきて 「皆がおかあちゃんによろしく―、て」 と伝えると、「ありがたいことやなあ。娘の友だちが皆で私のことを気づこうてくれはる」と喜んでいた母が、 まさか翌朝起きてこないとは一前日まで普通に過ごして、誰も知らないうちに亡くなったことについては、たぶん母の本望であったと思われます。 しかし、子どもの立場からは、長くても暫くでもつきっきりの介護がしたかったし、覚悟を決める時間が欲しかった、と切実に思います。今までのあれもこれも、お礼をいう暇もなかったのが残念です。
私が東京から通うことを、母の近所に住んでいる兄夫婦は「1週間くらい」と軽く考えていて、それについては不満でした。母と実際に一緒にいる時間でいうと、 1週間の私のほうが、別居して毎日20~30分程度の兄夫婦よりはずっとヘビーであることが、ある黄味では母自身にも、なかなか理解されませんでした。
滞在中の私が友だちと出かけ、帰ってきて 「皆がおかあちゃんによろしく―、て」 と伝えると、「ありがたいことやなあ。娘の友だちが皆で私のことを気づこうてくれはる」と喜んでいた母が、 まさか翌朝起きてこないとは一前日まで普通に過ごして、誰も知らないうちに亡くなったことについては、たぶん母の本望であったと思われます。 しかし、子どもの立場からは、長くても暫くでもつきっきりの介護がしたかったし、覚悟を決める時間が欲しかった、と切実に思います。今までのあれもこれも、お礼をいう暇もなかったのが残念です。
(会報パオッコ14号より)
体験談:012
K・Hさん(東京都 50代男性)
![]() 熊本県熊本市で二人暮らしの両親はともに78歳で、父は要支援1、母は障害者1級。 父は脳梗塞が直接の原因で身体動作が少し鈍く、昨年、自損事故を起こして自動車の運転をようやくあきらめてもらった。現在週1回リハビリセンターに通っている。。
熊本県熊本市で二人暮らしの両親はともに78歳で、父は要支援1、母は障害者1級。 父は脳梗塞が直接の原因で身体動作が少し鈍く、昨年、自損事故を起こして自動車の運転をようやくあきらめてもらった。現在週1回リハビリセンターに通っている。。
![]() 私のほかに姉、弟と、子どもは3人いるが、東京、大阪でそれぞれ仕事をしており、なかなか熊本にUターンできない状況。両親は本音では誰かに帰ってきてもらいたいのだろうが、さすがにもうあきらめてしまったようだ。
私のほかに姉、弟と、子どもは3人いるが、東京、大阪でそれぞれ仕事をしており、なかなか熊本にUターンできない状況。両親は本音では誰かに帰ってきてもらいたいのだろうが、さすがにもうあきらめてしまったようだ。
![]() 両親はさほど社交的ではないので、近所づきあいはほどほど、それぞれ囲碁や詩吟といった趣味の同好のおつきあいはある様子。親戚は高齢化して、近くに頼れる人はいない。特に母方の親戚とは仲も悪く、こちらも気を使う。
子ども3人が2カ月おきに交代で様子を見に行っている。姉弟仲がいいのが救い。姉は女手として、弟は家電や携帯・パソコンまわりの技術的なアドバイザーとして、それぞれ活躍してくれる。 緊急の帰省以外には<特割>を活用。最近では、実家に泊まると布団の準備などでかえって母の負担になるので、ホテルに1、2泊している。
頼りにしているのは、包括支援センターのソーシャルワーカーさん。初めて介護保険を申請するときから親身に相談に乗っていただいた。「お母さんのことも含め、生活全般なんでん(何でも)、私に言ってください」とざっくばらんなたいへん信頼できるかたで、帰省する前などにメールで連絡とりあって事前打ち合わせをしている。
父は被爆者でもあり、また母もペースメーカーをつけて障害者1級になったので、国や自治体のさまざまな公的支援を利用している。ただ、昨年、障害者手続きをしたときは、書類の多さに閉口したが。遠方まで歩けないので、子どもたちからタクシーチケットをプレゼントして、買い物などにもできるだけタクシーを利用してもらっている。使った分だけ、私たちに請求がくる。タクシー会社がよくわかってくれているのも、助かっている。
両親はさほど社交的ではないので、近所づきあいはほどほど、それぞれ囲碁や詩吟といった趣味の同好のおつきあいはある様子。親戚は高齢化して、近くに頼れる人はいない。特に母方の親戚とは仲も悪く、こちらも気を使う。
子ども3人が2カ月おきに交代で様子を見に行っている。姉弟仲がいいのが救い。姉は女手として、弟は家電や携帯・パソコンまわりの技術的なアドバイザーとして、それぞれ活躍してくれる。 緊急の帰省以外には<特割>を活用。最近では、実家に泊まると布団の準備などでかえって母の負担になるので、ホテルに1、2泊している。
頼りにしているのは、包括支援センターのソーシャルワーカーさん。初めて介護保険を申請するときから親身に相談に乗っていただいた。「お母さんのことも含め、生活全般なんでん(何でも)、私に言ってください」とざっくばらんなたいへん信頼できるかたで、帰省する前などにメールで連絡とりあって事前打ち合わせをしている。
父は被爆者でもあり、また母もペースメーカーをつけて障害者1級になったので、国や自治体のさまざまな公的支援を利用している。ただ、昨年、障害者手続きをしたときは、書類の多さに閉口したが。遠方まで歩けないので、子どもたちからタクシーチケットをプレゼントして、買い物などにもできるだけタクシーを利用してもらっている。使った分だけ、私たちに請求がくる。タクシー会社がよくわかってくれているのも、助かっている。
![]() 昨年帰省したとき、少しでも頼りになる人を増やしたいとの思いから、父にことわって近くの民生委員の方に手みやげ持参で挨拶に行った。すると、母から「たまに帰ってきて人間関係もわからずに勝手に挨拶に行くな」とこっぴどく叱られてしまった。民生委員のご婦人に対してこころよく思っていなかったことを初めて知った次第。東京に戻るときも口もきいてくれず、おおいに反省したことがあった。母は、最近、攻撃的な性格をみせており、父の主治医や親戚の悪口を言ったり、あるいは姉に対しても強くあたったりする。姉弟でこのような情報を共有して同じ轍を踏まないよう、気を使っている。
親とのコミュニケーションには姉弟含め家族の特割がきくソフトバンクの携帯を利用。しっかり理解してもらいたい内容はメールも送って文字を読んでもらうのが一番のようだ。こちらも電話口のストレスを感じなくてすむ。また、親もこちらの情報を知りたいようで、できるだけ近況報告メールを送る。
最近横行している年寄りを狙った悪質な商売には、包括支援センターでも注意を呼びかけてくれるが、父が特に人がよすぎて、セールスを家にあげてしまうなど心配のたねは尽きない。アイホンをとりつけ、玄関は施錠して信頼できる相手かどうか必ず確認するよう注意しても、鍵をかけていないことが多い。また、そろそろ家のバリアフリー化も提案しているが、「必要ない」の一点張り。風呂場など危ないところをなんとかしたいが、こちらからあまり強硬にも言えない。
昨年帰省したとき、少しでも頼りになる人を増やしたいとの思いから、父にことわって近くの民生委員の方に手みやげ持参で挨拶に行った。すると、母から「たまに帰ってきて人間関係もわからずに勝手に挨拶に行くな」とこっぴどく叱られてしまった。民生委員のご婦人に対してこころよく思っていなかったことを初めて知った次第。東京に戻るときも口もきいてくれず、おおいに反省したことがあった。母は、最近、攻撃的な性格をみせており、父の主治医や親戚の悪口を言ったり、あるいは姉に対しても強くあたったりする。姉弟でこのような情報を共有して同じ轍を踏まないよう、気を使っている。
親とのコミュニケーションには姉弟含め家族の特割がきくソフトバンクの携帯を利用。しっかり理解してもらいたい内容はメールも送って文字を読んでもらうのが一番のようだ。こちらも電話口のストレスを感じなくてすむ。また、親もこちらの情報を知りたいようで、できるだけ近況報告メールを送る。
最近横行している年寄りを狙った悪質な商売には、包括支援センターでも注意を呼びかけてくれるが、父が特に人がよすぎて、セールスを家にあげてしまうなど心配のたねは尽きない。アイホンをとりつけ、玄関は施錠して信頼できる相手かどうか必ず確認するよう注意しても、鍵をかけていないことが多い。また、そろそろ家のバリアフリー化も提案しているが、「必要ない」の一点張り。風呂場など危ないところをなんとかしたいが、こちらからあまり強硬にも言えない。
![]() 心配することばかりだが、両親とまめに連絡をとり、姉弟との連携、包括支援センターとの連携をとって、いざというときの備えをいまからしようと思っている。財産や収入の明細を教えてもらい、親の気持ちを大切にしながら、今後の両親の生活設計を考えていきたい。
心配することばかりだが、両親とまめに連絡をとり、姉弟との連携、包括支援センターとの連携をとって、いざというときの備えをいまからしようと思っている。財産や収入の明細を教えてもらい、親の気持ちを大切にしながら、今後の両親の生活設計を考えていきたい。
(会報パオッコ12号より)
体験談:011
M・Iさん(埼玉県 50代女性)
![]() 栃木県にひとり暮らしの母は79歳。父は私が子どものころ亡くなった。曲がりぎみだった腰が最近さらに曲がり、少し動いては少し休む、といった様子ではあるが、電動三輪車でひとりあちこちに買いものに出かけたりしている。
栃木県にひとり暮らしの母は79歳。父は私が子どものころ亡くなった。曲がりぎみだった腰が最近さらに曲がり、少し動いては少し休む、といった様子ではあるが、電動三輪車でひとりあちこちに買いものに出かけたりしている。
![]() 51歳の私と50歳の妹は、埼玉県と神奈川県に在住。それぞれに家族があり、妹のほうは子どもがいないものの義母と同居で、会社勤めの身でもある。また、我が家の3DKの住まいでは、とても母を呼び寄せて同居するだけのスペースがない。さらには、母の性格から推して、私の夫や子どもたちとのトラブルが容易に予想される。それどころか、私自身がノイローゼになってしまうのではないかという危惧さえある。
母自身も、田舎に親戚や友人、知人が多く、ひとり暮らしのほうが気楽といった点からも、埼玉までは来たがらない。
51歳の私と50歳の妹は、埼玉県と神奈川県に在住。それぞれに家族があり、妹のほうは子どもがいないものの義母と同居で、会社勤めの身でもある。また、我が家の3DKの住まいでは、とても母を呼び寄せて同居するだけのスペースがない。さらには、母の性格から推して、私の夫や子どもたちとのトラブルが容易に予想される。それどころか、私自身がノイローゼになってしまうのではないかという危惧さえある。
母自身も、田舎に親戚や友人、知人が多く、ひとり暮らしのほうが気楽といった点からも、埼玉までは来たがらない。
![]() 妹の事情から必然的に、母の老後の世話は私が一手に引き受けることになると予想され、3年前に、実家へ通うため運転免許を取得(7カ月かかった)。現在、私が月に2回というペースで埼玉県の自宅と栃木県の母のもとを往復して、母のひとり暮らしを支えているつもりだ。
母は1週間に1度、車での送迎付きデイサービスに行くのをいちばんの楽しみにしている。将来、ひとりで買いものに行けなくなったら、私が今よりひんぱんに帰省するつもり。ちなみに、実家の近所のひとり暮らし高齢者で、ホームヘルパーを頼んでいる人は誰もいない。他人が家に入ることに抵抗がある、と母は言う。そういう土地柄なのだろう。寝たきりになったら?それを考えると頭が痛いが、そのときの状況に応じて最善と思える方法をとるしかない。
妹の事情から必然的に、母の老後の世話は私が一手に引き受けることになると予想され、3年前に、実家へ通うため運転免許を取得(7カ月かかった)。現在、私が月に2回というペースで埼玉県の自宅と栃木県の母のもとを往復して、母のひとり暮らしを支えているつもりだ。
母は1週間に1度、車での送迎付きデイサービスに行くのをいちばんの楽しみにしている。将来、ひとりで買いものに行けなくなったら、私が今よりひんぱんに帰省するつもり。ちなみに、実家の近所のひとり暮らし高齢者で、ホームヘルパーを頼んでいる人は誰もいない。他人が家に入ることに抵抗がある、と母は言う。そういう土地柄なのだろう。寝たきりになったら?それを考えると頭が痛いが、そのときの状況に応じて最善と思える方法をとるしかない。
![]() 例えば、私の顔を見るなり、「M子は仕事がキライだからなあ。××のおばちゃんに似たんだろ」。30分おきに公園やコンビニで休憩をとりながら車を運転すること4時間(夫の運転なら2時間のところ)、やっと実家にたどりついたばかりで疲労こんぱいの私には、そういう母の情け容赦のない口調がこたえる。早くに夫を亡くした母自身の苦労に比べ、私がのほほんと専業主婦でいる のがおもしろくないのだろうとすぐに察せられるのだが、以前から似たような発言があったとはいえ、これほど辛辣ではなかった。ここ2~3週間、私が帰省する間があいたので淋しかったのだろうか、近所の人とトラブルでもあって、そのストレスをぶつけているだけなのだろうか?それとも、ここ数日、体調があまりよくないのを知りつつ、自分の家庭の都合で私が帰省を先延ばしにしたのを根にもっているのだろうか?
昔から自己中心的なもの言いをする母だったが、最近それがエスカレートしているような気がする。認知症の前兆ではないだろうか? しかし、そんな私の不安をよそに、母は延々と、さらに昔のことを引っぱり出してきては私を責めたてる。
例えば、私の顔を見るなり、「M子は仕事がキライだからなあ。××のおばちゃんに似たんだろ」。30分おきに公園やコンビニで休憩をとりながら車を運転すること4時間(夫の運転なら2時間のところ)、やっと実家にたどりついたばかりで疲労こんぱいの私には、そういう母の情け容赦のない口調がこたえる。早くに夫を亡くした母自身の苦労に比べ、私がのほほんと専業主婦でいる のがおもしろくないのだろうとすぐに察せられるのだが、以前から似たような発言があったとはいえ、これほど辛辣ではなかった。ここ2~3週間、私が帰省する間があいたので淋しかったのだろうか、近所の人とトラブルでもあって、そのストレスをぶつけているだけなのだろうか?それとも、ここ数日、体調があまりよくないのを知りつつ、自分の家庭の都合で私が帰省を先延ばしにしたのを根にもっているのだろうか?
昔から自己中心的なもの言いをする母だったが、最近それがエスカレートしているような気がする。認知症の前兆ではないだろうか? しかし、そんな私の不安をよそに、母は延々と、さらに昔のことを引っぱり出してきては私を責めたてる。
![]() 出来る限り長く、今のこの生活スタイルを持続させたいと考えている。 2カ月ごとに帰省する妹に対しても、1カ月に2度帰省する私に対しても、野菜の切り方ひとつにも大きすぎる、小さすぎる、長すぎる、短すぎると必ず文句をつけ、せっかくつくった味噌汁も捨てて自分好みの味につくり直すような母ではあるが、この先もはや10年健在だろうかと思えば、我慢もできる。父亡きあと苦労して私たちを育ててくれた母なので、できるかぎりのことはしてあげたい。将来、私自身が、こうしてあげればよかった、ああしてあげればよかったと後悔しないために。
出来る限り長く、今のこの生活スタイルを持続させたいと考えている。 2カ月ごとに帰省する妹に対しても、1カ月に2度帰省する私に対しても、野菜の切り方ひとつにも大きすぎる、小さすぎる、長すぎる、短すぎると必ず文句をつけ、せっかくつくった味噌汁も捨てて自分好みの味につくり直すような母ではあるが、この先もはや10年健在だろうかと思えば、我慢もできる。父亡きあと苦労して私たちを育ててくれた母なので、できるかぎりのことはしてあげたい。将来、私自身が、こうしてあげればよかった、ああしてあげればよかったと後悔しないために。
(会報パオッコ8号より)
体験談:010
K・Hさん(東京都 40代女性)
![]() 義母は81歳。千葉県在住。夫婦ふたり暮らしだった14年前に夫を亡くし、数年のひとり暮らしを経たのち長男(50代、独身)と同居。足が弱いなりに自転車での行動範囲はかなり広かったのに、03年、転んで大腿骨骨折、手術して1カ月ほど入院したのをきっかけに、めっきり不活発に。認知症の疑い濃厚ながら、病院への嫌悪がはなはだしく要介護認定申請もできずにいたところ、今年8月に脳梗塞で倒れて救急車で入院。要介護3に認定され、経過措置として自宅近所に転院、施設への入所を模索中。
義母は81歳。千葉県在住。夫婦ふたり暮らしだった14年前に夫を亡くし、数年のひとり暮らしを経たのち長男(50代、独身)と同居。足が弱いなりに自転車での行動範囲はかなり広かったのに、03年、転んで大腿骨骨折、手術して1カ月ほど入院したのをきっかけに、めっきり不活発に。認知症の疑い濃厚ながら、病院への嫌悪がはなはだしく要介護認定申請もできずにいたところ、今年8月に脳梗塞で倒れて救急車で入院。要介護3に認定され、経過措置として自宅近所に転院、施設への入所を模索中。
![]() 次男の夫は早くから親もとを離れていたうえ、兄が実家に戻ったことで私たちの同居は想定外となった。それでなくとも、気ままなペースでの生活を望み、結果的にはどうあれ子どもたちを煩わせたくないと言い張る母のほうからも、兄の同居ですら予定外だったはず。
ただし、父の死後の事務処理一切を引き受けて以来、夫が金銭管理のできない母のフォローをし続けてきた。家計に無頓着な兄が同居してからはなおさら放っておけなくなったようだし、実家のふたりはろくにコミュニケーションのない日々、親戚づきあいはなくご近所づきあいも薄い状況なので、片道2時間ほどに住む次男夫婦としてなるべく足しげく通うほかない。
次男の夫は早くから親もとを離れていたうえ、兄が実家に戻ったことで私たちの同居は想定外となった。それでなくとも、気ままなペースでの生活を望み、結果的にはどうあれ子どもたちを煩わせたくないと言い張る母のほうからも、兄の同居ですら予定外だったはず。
ただし、父の死後の事務処理一切を引き受けて以来、夫が金銭管理のできない母のフォローをし続けてきた。家計に無頓着な兄が同居してからはなおさら放っておけなくなったようだし、実家のふたりはろくにコミュニケーションのない日々、親戚づきあいはなくご近所づきあいも薄い状況なので、片道2時間ほどに住む次男夫婦としてなるべく足しげく通うほかない。
![]() 義母が元気なころは月1回ほど、骨折後は少なくとも月2回、銀行関係の処理をする夫に私も同行、なるべく4人そろって(家族総出というか?)外食するというパターンが定着していた。実家を訪れる際には、話し相手になるほか、折々に布団を干したり、衣類の手入れや掃除に気を配ったり。
介護保険にせよ民間のものにせよサービスを利用するには、実家の生活が不規則すぎて、導入を考えるたびにひたすら消極的になっていき、ついに何ひとつ利用せずじまい。例えば隣人がごみ出しをしてくれるのに対して、満杯にならないうちに出されると袋が無駄だとかプライバシーをのぞかれてしまうとか義母は不平を言っていた。その他、家族以外の人間への不信を聞かされるたびに、提案する気持ちも萎える。
義母が元気なころは月1回ほど、骨折後は少なくとも月2回、銀行関係の処理をする夫に私も同行、なるべく4人そろって(家族総出というか?)外食するというパターンが定着していた。実家を訪れる際には、話し相手になるほか、折々に布団を干したり、衣類の手入れや掃除に気を配ったり。
介護保険にせよ民間のものにせよサービスを利用するには、実家の生活が不規則すぎて、導入を考えるたびにひたすら消極的になっていき、ついに何ひとつ利用せずじまい。例えば隣人がごみ出しをしてくれるのに対して、満杯にならないうちに出されると袋が無駄だとかプライバシーをのぞかれてしまうとか義母は不平を言っていた。その他、家族以外の人間への不信を聞かされるたびに、提案する気持ちも萎える。
![]() ハハに対するアニの態度や、夫の実家の生活ぶりが肌に合わず、はっきりと家事などで頼りにされるほうがましだと思うくらい苦痛だった。マゴがいれば場がはなやいだだろうにと、私たちに子どもがいないことが悔しくなることもしばしば。「もうイヤだね、毎月毎月」と、私からは言いにくかったせりふが今年に入ってついに夫の口から出たところだった。
入院中のハハの世話で私が当面できることは洗濯くらいで、交通費に見合うのかとか、ほかにできることはないのかとか、いま思いつく苦労といえばやはり気苦労のたぐい。当初、話すことは支離滅裂でも「うちに帰らなくちゃ」だけは一貫していたのに、ベッドに寝かせきりのあいだにその意志も薄れてきたことに胸が痛む。施設探しも、アニに任せてはおけないのだろうが、私はどう口出し手出ししたらいいのか困惑する。
ハハに対するアニの態度や、夫の実家の生活ぶりが肌に合わず、はっきりと家事などで頼りにされるほうがましだと思うくらい苦痛だった。マゴがいれば場がはなやいだだろうにと、私たちに子どもがいないことが悔しくなることもしばしば。「もうイヤだね、毎月毎月」と、私からは言いにくかったせりふが今年に入ってついに夫の口から出たところだった。
入院中のハハの世話で私が当面できることは洗濯くらいで、交通費に見合うのかとか、ほかにできることはないのかとか、いま思いつく苦労といえばやはり気苦労のたぐい。当初、話すことは支離滅裂でも「うちに帰らなくちゃ」だけは一貫していたのに、ベッドに寝かせきりのあいだにその意志も薄れてきたことに胸が痛む。施設探しも、アニに任せてはおけないのだろうが、私はどう口出し手出ししたらいいのか困惑する。
![]() 自分の実家の親戚・近所づきあいの濃さとつい比べて、ハハの状況を不憫に感じるのは筋ちがいだと考えることにした。築いてきた人間関係の上にある今なのでしょう。私の役どころは、ハハのプライベートな資源のなかでは貴重な“女手”、損な役回りに思える夫の“同志”かな。
自分の実家の親戚・近所づきあいの濃さとつい比べて、ハハの状況を不憫に感じるのは筋ちがいだと考えることにした。築いてきた人間関係の上にある今なのでしょう。私の役どころは、ハハのプライベートな資源のなかでは貴重な“女手”、損な役回りに思える夫の“同志”かな。
(会報パオッコ7号より)
体験談:009
N子さん(東京都 50代女性)
![]() 東京。義父(88歳、要介護3)は軽い認知症があり、杖なしでは歩けない。我が家から1時間内の有料老人ホームに入居して1年半。2004年10月までは新潟県在住。もともと、義父が自宅では生活できなくなったら、最終的には地元施設へ入所をと考えていた。短期間に予期せぬ展開と紆余曲折を経て、東京都内のしかも我が家の近くにいいところが見つかってほんとに助かっている。
東京。義父(88歳、要介護3)は軽い認知症があり、杖なしでは歩けない。我が家から1時間内の有料老人ホームに入居して1年半。2004年10月までは新潟県在住。もともと、義父が自宅では生活できなくなったら、最終的には地元施設へ入所をと考えていた。短期間に予期せぬ展開と紆余曲折を経て、東京都内のしかも我が家の近くにいいところが見つかってほんとに助かっている。
![]() 10年前、義母が倒れたのを期に、遠距離介護が始まる。義父は、いつか息子(私の夫)が田舎に帰って同居するものと思っていた。が、東京で40年近く勤め、いまさらUターンは無理と判断した夫は、親の思いを裏切る申し訳なさもあったのか、どんなにたいへんでも週末の帰省を続け、私も同行。
10年前、義母が倒れたのを期に、遠距離介護が始まる。義父は、いつか息子(私の夫)が田舎に帰って同居するものと思っていた。が、東京で40年近く勤め、いまさらUターンは無理と判断した夫は、親の思いを裏切る申し訳なさもあったのか、どんなにたいへんでも週末の帰省を続け、私も同行。
![]() 3年半は毎週末、その後月2~3回のペースで帰省して、ひとり暮らしの義父を支えてきた。さまざまなサービスを導入、家の設備も整え、その都度起きるやっかいな問題も解決して、ようやく軌道に乗せたと思っていたところへ、突然の地震。親戚の連携プレーで間一髪助かったが、家は半壊。義父を預かってくれた妹と連絡をとり続けたあげく3日後に空路東京の我が家へ連れ帰り、予定外の同居となった。義父にとっても、何がなんだかわからなかったに違いない。
しかし、同居生活にはたちまち無理がきて我が家の生活が危うくなり、ホーム探しを開始。とりあえずショートステイ先を探し、徐々に日を増やして我が家との行き来を繰り返しては義父に慣れてもらいつつ、情報を集めては見学、体験入所した。都内では入居金が高く、義父の財産でなんとか生涯まかなうには不安だったが、あきらめかけたころ、開所まもない今のホームに出会い、幸運にもそれまででいちばん気に入った。特に、夫が「ここなら」と言ったのはうれしかった。今は、必要に応じてホームとFAXでやりとりし、月に1~2回面会に義父のもとを訪れている。
3年半は毎週末、その後月2~3回のペースで帰省して、ひとり暮らしの義父を支えてきた。さまざまなサービスを導入、家の設備も整え、その都度起きるやっかいな問題も解決して、ようやく軌道に乗せたと思っていたところへ、突然の地震。親戚の連携プレーで間一髪助かったが、家は半壊。義父を預かってくれた妹と連絡をとり続けたあげく3日後に空路東京の我が家へ連れ帰り、予定外の同居となった。義父にとっても、何がなんだかわからなかったに違いない。
しかし、同居生活にはたちまち無理がきて我が家の生活が危うくなり、ホーム探しを開始。とりあえずショートステイ先を探し、徐々に日を増やして我が家との行き来を繰り返しては義父に慣れてもらいつつ、情報を集めては見学、体験入所した。都内では入居金が高く、義父の財産でなんとか生涯まかなうには不安だったが、あきらめかけたころ、開所まもない今のホームに出会い、幸運にもそれまででいちばん気に入った。特に、夫が「ここなら」と言ったのはうれしかった。今は、必要に応じてホームとFAXでやりとりし、月に1~2回面会に義父のもとを訪れている。
![]() 同居中の苦労が記憶に新しい。夜中、ベランダの戸が開いていると思ったら、おしっこ中。介助なしでは無理だったはずなのに気持ちよさそうに入浴中で、湯が台所まであふれている。残りものを食べたらしく、朝見ると冷蔵庫の中は荒らされ扉は半開き──毎晩の事件に家族はフラフラ。日中ひとりで一緒にいる私は、一歩も外に出ることができなくなってしまった。
あれから1年半、先日は自分の息子と孫を間違えているふうだったし、ホームからはFAXで、おはじきを飴と思って口にしたとの報告もあった。ここに来て急に認知度も身体能力も低下したようだ。
同居中の苦労が記憶に新しい。夜中、ベランダの戸が開いていると思ったら、おしっこ中。介助なしでは無理だったはずなのに気持ちよさそうに入浴中で、湯が台所まであふれている。残りものを食べたらしく、朝見ると冷蔵庫の中は荒らされ扉は半開き──毎晩の事件に家族はフラフラ。日中ひとりで一緒にいる私は、一歩も外に出ることができなくなってしまった。
あれから1年半、先日は自分の息子と孫を間違えているふうだったし、ホームからはFAXで、おはじきを飴と思って口にしたとの報告もあった。ここに来て急に認知度も身体能力も低下したようだ。
![]() 思いがけない展開になったが、結果よし。貴重な体験で、いざというときほんとうに力になってくれる人のありがたさ、日ごろのつきあいの大切さも実感。これからも義父訪問と、実母(新潟県)の遠距離介護は続く。双方の実家の始末も頭が痛い問題。人さまにお任せしてひと息つける今を大切に、次の波を乗り切れたらと思う。
自身の老いも感じる。子どもたちをあてにせず、寄りかかるのは他人さまに。それでもしかたなくなったら「ごめん、よろしくね! !」と言える老人になりたい。
思いがけない展開になったが、結果よし。貴重な体験で、いざというときほんとうに力になってくれる人のありがたさ、日ごろのつきあいの大切さも実感。これからも義父訪問と、実母(新潟県)の遠距離介護は続く。双方の実家の始末も頭が痛い問題。人さまにお任せしてひと息つける今を大切に、次の波を乗り切れたらと思う。
自身の老いも感じる。子どもたちをあてにせず、寄りかかるのは他人さまに。それでもしかたなくなったら「ごめん、よろしくね! !」と言える老人になりたい。
(会報パオッコ6号より)
体験談:008
Y子さん(東京都 50代女性)
![]() 東京。母80歳。独居9年目。父の生前から夫婦で入会していた<在宅介護を支える会>のホームドクターが2週に1度往診。肺と気管支が弱いため現在要支援で、そうじ週1回。生活の支障ナシ。
東京。母80歳。独居9年目。父の生前から夫婦で入会していた<在宅介護を支える会>のホームドクターが2週に1度往診。肺と気管支が弱いため現在要支援で、そうじ週1回。生活の支障ナシ。
![]() 父が急死したショックで激ヤセした母は、ずっと自宅でひとり暮らしでもかまわないと言う一方で、寝込むようになったら不安なので娘3人のうち誰かがいずれ同居してくれれば安心とも言う。当初ドクターにも同居を勧められた。
姉(茨城県)はウツ的症状を抱え、妹(東京都)は子どもが小さく仕事の関係上無理なので、同じ東京で2時間以内で通え、時間の都合がつけられる私が、将来の同居前提で通い始めた。 しかし実際には、両家の膨大な物の片づけ、価値観の違いなど、とても同居は無理で、結局通い9年目を迎える。
父が急死したショックで激ヤセした母は、ずっと自宅でひとり暮らしでもかまわないと言う一方で、寝込むようになったら不安なので娘3人のうち誰かがいずれ同居してくれれば安心とも言う。当初ドクターにも同居を勧められた。
姉(茨城県)はウツ的症状を抱え、妹(東京都)は子どもが小さく仕事の関係上無理なので、同じ東京で2時間以内で通え、時間の都合がつけられる私が、将来の同居前提で通い始めた。 しかし実際には、両家の膨大な物の片づけ、価値観の違いなど、とても同居は無理で、結局通い9年目を迎える。
![]() ①防犯…父が亡くなった際、空き巣に入られているので、建具を取り替え、二重の鍵を取り付け、通帳・権利書などは貸金庫に預け、表札二世帯分をつけた。
②母の居室改築…和室2間を1部屋にし、床暖房・バスユニット・キッチンコーナーを入れた(介護保険適用外)。冷え性の母には床暖房とバスユニットはとても快適。
③ヘルパーのそうじ…居室が散らかりやすく、来る日は必死で片づけている(私は極力口出ししないようにしている)。
④緊急対策…ホームドクターに直接連絡がつく。救急薬を預かっている。母の携帯からワンタッチボタンで私の携帯につながる。
⑤近所の好意…ひとり暮らしは実家だけなので、ごみ捨て・安否など気にかけてくれる。隣家は、緊急ブザー配線を自ら申し出てくれて母の居室に設置(未使用)、私の電話番号を控えてくれている。
⑥通いは毎月7日間前後(姉・妹は年に2~3回)。母から仕事としての報酬を受け取っている。
①防犯…父が亡くなった際、空き巣に入られているので、建具を取り替え、二重の鍵を取り付け、通帳・権利書などは貸金庫に預け、表札二世帯分をつけた。
②母の居室改築…和室2間を1部屋にし、床暖房・バスユニット・キッチンコーナーを入れた(介護保険適用外)。冷え性の母には床暖房とバスユニットはとても快適。
③ヘルパーのそうじ…居室が散らかりやすく、来る日は必死で片づけている(私は極力口出ししないようにしている)。
④緊急対策…ホームドクターに直接連絡がつく。救急薬を預かっている。母の携帯からワンタッチボタンで私の携帯につながる。
⑤近所の好意…ひとり暮らしは実家だけなので、ごみ捨て・安否など気にかけてくれる。隣家は、緊急ブザー配線を自ら申し出てくれて母の居室に設置(未使用)、私の電話番号を控えてくれている。
⑥通いは毎月7日間前後(姉・妹は年に2~3回)。母から仕事としての報酬を受け取っている。
![]() 同居する予定だったので、一部の改築・改装に伴う片づけをすべて私ひとりでやったり、父の書斎の整理、庭の手入れなどの肉体労働でも、他人には頼めないことって意外と多い。五十肩で苦しんでからは庭は植木屋に任せる以外手抜き。
息子が大学入学した際に、用心棒を期待して実家の二階に住まわせたが、かえって母のストレスが増え、表情まで変わってしまい、私は母と息子のトラブルを解決すべく前以上に通うはめに。結局3年目で息子は出ていった。母は静かなマイペースの生活を乱されるのがいちばんイヤだということを思い知った。孫といえども若い男が苦手ということも! 母の本心がわかり、娘夫婦との同居も厳しいだろうと悟った。
昨春、急性気管支炎で3週間入院した際、記憶の混乱が生じたため、退院後約1カ月、もとの生活に戻れるまで実家にとどまった。そのため、たった3カ月でパートを辞めざるをえなかったが、しかたない。その後、再度母娘全員で今後の相談をした。母は、同居のための片付けや耐震改築などをする気力はもうないので、このままの状態でいいという。
物の整理が苦手な母を手伝うことで、母の価値観と衝突して疲れることもあり、スムーズにひとり暮らしを続けるためにどこまで娘として立ち入るか、いまだに悩んでいる。料理や火の始末の不安も増してきた。
同居する予定だったので、一部の改築・改装に伴う片づけをすべて私ひとりでやったり、父の書斎の整理、庭の手入れなどの肉体労働でも、他人には頼めないことって意外と多い。五十肩で苦しんでからは庭は植木屋に任せる以外手抜き。
息子が大学入学した際に、用心棒を期待して実家の二階に住まわせたが、かえって母のストレスが増え、表情まで変わってしまい、私は母と息子のトラブルを解決すべく前以上に通うはめに。結局3年目で息子は出ていった。母は静かなマイペースの生活を乱されるのがいちばんイヤだということを思い知った。孫といえども若い男が苦手ということも! 母の本心がわかり、娘夫婦との同居も厳しいだろうと悟った。
昨春、急性気管支炎で3週間入院した際、記憶の混乱が生じたため、退院後約1カ月、もとの生活に戻れるまで実家にとどまった。そのため、たった3カ月でパートを辞めざるをえなかったが、しかたない。その後、再度母娘全員で今後の相談をした。母は、同居のための片付けや耐震改築などをする気力はもうないので、このままの状態でいいという。
物の整理が苦手な母を手伝うことで、母の価値観と衝突して疲れることもあり、スムーズにひとり暮らしを続けるためにどこまで娘として立ち入るか、いまだに悩んでいる。料理や火の始末の不安も増してきた。
![]() 不安から、ついキツイ言い方をして母をショボンとさせてしまうことや、私自身が母の犠牲になっていると感じることのないようにするためには、私のための時間をもっと確保すべきだと思った。で、実家滞在のあいだに友人とのおしゃべりや散策を楽しみ、亡き父と共同で作る予定だった本を完成させた。母が80の峠を元気に楽しく越える手助けをしながら、3年後に夫の定年を控えて、自分の老後の設計もしたい。
不安から、ついキツイ言い方をして母をショボンとさせてしまうことや、私自身が母の犠牲になっていると感じることのないようにするためには、私のための時間をもっと確保すべきだと思った。で、実家滞在のあいだに友人とのおしゃべりや散策を楽しみ、亡き父と共同で作る予定だった本を完成させた。母が80の峠を元気に楽しく越える手助けをしながら、3年後に夫の定年を控えて、自分の老後の設計もしたい。
(会報パオッコ5号より)
体験談:007
C・Kさん(東京都 50代女性)
![]() 大阪府北部。父83歳、母77歳、夫婦2人暮らし。去年の夏、父が過去2回罹病したガンの消化器へ転移が発見され、その治療のために入院。高齢だということと余病があったため手術は断念し、放射線と抗ガン剤投与による治療が終了後、退院して自宅介護。母は高血圧の通院治療をしながらも一応元気。3カ月弱の入院で足が弱ってしまった父を、55年ほど住んでいる今の土地で母1人が介護奮闘中。
大阪府北部。父83歳、母77歳、夫婦2人暮らし。去年の夏、父が過去2回罹病したガンの消化器へ転移が発見され、その治療のために入院。高齢だということと余病があったため手術は断念し、放射線と抗ガン剤投与による治療が終了後、退院して自宅介護。母は高血圧の通院治療をしながらも一応元気。3カ月弱の入院で足が弱ってしまった父を、55年ほど住んでいる今の土地で母1人が介護奮闘中。
![]() 両親は「子どもたちは自分たちの幸福な生活を第1に考えるべきで、結婚するときの条件に近くに住んでほしいという願いはない」という考え方だったため、3人の子どもたちはそれぞれ仕事を持ち、みな遠くで生活をしている。私も会社勤めの後フリーで仕事をしているので、介護のために大阪に長期滞在は難しいというのが現状。ただ、父の具合が今よりも悪くなったり、母からの要望があったりした場合はできるだけ寄り添うつもりでいる。このことは、夫も子どもたちも暗黙の了解をしてくれている。
両親は「子どもたちは自分たちの幸福な生活を第1に考えるべきで、結婚するときの条件に近くに住んでほしいという願いはない」という考え方だったため、3人の子どもたちはそれぞれ仕事を持ち、みな遠くで生活をしている。私も会社勤めの後フリーで仕事をしているので、介護のために大阪に長期滞在は難しいというのが現状。ただ、父の具合が今よりも悪くなったり、母からの要望があったりした場合はできるだけ寄り添うつもりでいる。このことは、夫も子どもたちも暗黙の了解をしてくれている。
![]() 介護が必要なかったときは、1カ月に1回(2~3日)帰省したり、一緒に旅行をしたりして「昔のままの親子感覚」をお互いに楽しんでいたが、今回のガンの罹病からは1カ月に2回(それぞれ1週間程度)帰省し「介護を中心とした新しい親子関係」の築きをお互いに慈しんでいる。また、東京に帰ってからは1日おきに電話をして、父の様子や母のストレスからくる愚痴を聞くようにしている。在宅介護をするようになってからは「父の病状と介護についての表」を作成し、毎日母にそれに記入してもらうことにしている。その表は訪問診療の医師にも好評で、父の病状についての客観的な状況のほか、病状の不安や介護の問題点等が母の視点で書いてあるので、毎日の介護をしている母、医師、そして私の共通認識にも役に立っている。
介護保険はもちろん活用し、住宅改修やベッド等のレンタル、シャワーチェア等の購入をして、できるだけ快適に過ごせるようにしている。父は認知症も出ていないし、母が大変そうではあるが今のところ自分のペースでゆっくりと父の介護をやっているので、民間のサービスは利用していない。でも、そのうち必要になるかも……と思っている。
介護が必要なかったときは、1カ月に1回(2~3日)帰省したり、一緒に旅行をしたりして「昔のままの親子感覚」をお互いに楽しんでいたが、今回のガンの罹病からは1カ月に2回(それぞれ1週間程度)帰省し「介護を中心とした新しい親子関係」の築きをお互いに慈しんでいる。また、東京に帰ってからは1日おきに電話をして、父の様子や母のストレスからくる愚痴を聞くようにしている。在宅介護をするようになってからは「父の病状と介護についての表」を作成し、毎日母にそれに記入してもらうことにしている。その表は訪問診療の医師にも好評で、父の病状についての客観的な状況のほか、病状の不安や介護の問題点等が母の視点で書いてあるので、毎日の介護をしている母、医師、そして私の共通認識にも役に立っている。
介護保険はもちろん活用し、住宅改修やベッド等のレンタル、シャワーチェア等の購入をして、できるだけ快適に過ごせるようにしている。父は認知症も出ていないし、母が大変そうではあるが今のところ自分のペースでゆっくりと父の介護をやっているので、民間のサービスは利用していない。でも、そのうち必要になるかも……と思っている。
![]() 遠くに住んでいるので、父の不安や介護者である母のストレスや疲れをその場で聞いてあげることができず、歯がゆい思い。老人2人だけで住んでいるので、「刺激がない毎日」。元来父は地域でのコミュニケーションが少ないうえ、母も父の看護でどうしても地域とのふれあいが少なくなっている。そのことが、ますます運動不足や楽しみがない日々を呼び、輝きのない人生になっていくのではないか……?!とても憂慮している。そうならないために、私たち子どもはどうすればいいのでしょうか? 悩む毎日。
遠くに住んでいるので、父の不安や介護者である母のストレスや疲れをその場で聞いてあげることができず、歯がゆい思い。老人2人だけで住んでいるので、「刺激がない毎日」。元来父は地域でのコミュニケーションが少ないうえ、母も父の看護でどうしても地域とのふれあいが少なくなっている。そのことが、ますます運動不足や楽しみがない日々を呼び、輝きのない人生になっていくのではないか……?!とても憂慮している。そうならないために、私たち子どもはどうすればいいのでしょうか? 悩む毎日。
![]() 介護状態であるからこそ、父も母もその状態においての“楽しい毎日、楽しい時間”を送ってほしい!と思う。父ならば、何をすれば楽しく時間を過ごせるのか? 母ならば、どんなことをすれば介護のストレスを解消できるのか?そのために、遠距離にいる私にどのような方法とアクションしていけばいいのか?今回の帰省では、父や母たちと一緒にできる「ゲーム」(結構頭脳を使うゲームだったので、父の頭のトレーニングにもなったと思う)、そして父の介護をするまでは墨絵を書いていた母(父の介護を始めてからは余裕がなくやめてしまった)には、水彩色鉛筆と大人用塗り絵を持参。両方ともとても喜び楽しんでいたので、その他のいい案があれば……と思っているのですが、具体案を考えるのも1人では限界かも……。皆さんのお知恵を拝借したい!
介護状態であるからこそ、父も母もその状態においての“楽しい毎日、楽しい時間”を送ってほしい!と思う。父ならば、何をすれば楽しく時間を過ごせるのか? 母ならば、どんなことをすれば介護のストレスを解消できるのか?そのために、遠距離にいる私にどのような方法とアクションしていけばいいのか?今回の帰省では、父や母たちと一緒にできる「ゲーム」(結構頭脳を使うゲームだったので、父の頭のトレーニングにもなったと思う)、そして父の介護をするまでは墨絵を書いていた母(父の介護を始めてからは余裕がなくやめてしまった)には、水彩色鉛筆と大人用塗り絵を持参。両方ともとても喜び楽しんでいたので、その他のいい案があれば……と思っているのですが、具体案を考えるのも1人では限界かも……。皆さんのお知恵を拝借したい!
(会報パオッコ4号より)
体験談:006
Y・Mさん(神奈川県 50代女性)
![]() 山口県。父91歳、兄と2人暮らし。車で4、5分の所に姉の家族在住。13年前に母が他界し、3人暮らしから父と兄2人の生活となった。父は85歳を過ぎた頃から体力が徐々に衰え、2年前の6月に介護保険を申請。要介護1の診断を受けた。現在は要介護3である。兄は自営業のため、時間の融通がきくが、週3回のヘルパーさんの訪問と姉(仕事をしているので平日の夜、日曜日に実家へ行く)や姪の手助けで何とか父の世話をしている。近所の方がおかずを持って来てくれたり、父を心配して訪ねてくれるのも一助となっている
山口県。父91歳、兄と2人暮らし。車で4、5分の所に姉の家族在住。13年前に母が他界し、3人暮らしから父と兄2人の生活となった。父は85歳を過ぎた頃から体力が徐々に衰え、2年前の6月に介護保険を申請。要介護1の診断を受けた。現在は要介護3である。兄は自営業のため、時間の融通がきくが、週3回のヘルパーさんの訪問と姉(仕事をしているので平日の夜、日曜日に実家へ行く)や姪の手助けで何とか父の世話をしている。近所の方がおかずを持って来てくれたり、父を心配して訪ねてくれるのも一助となっている
![]() 父は元気な頃「住み慣れた我が家で最期を迎えたい」とよく言っていた。気の優しい兄はそれを尊重したいと思っており、自分が父の世話を最期までするつもりでいる。私達姉妹はそれに出来る限り協力するよう努めることにした。私に出来る事は年に数回帰省し、その間私が父の世話をし、兄姉の介護負担を軽減することであると認識したため、遠距離介護を選択した。
父は元気な頃「住み慣れた我が家で最期を迎えたい」とよく言っていた。気の優しい兄はそれを尊重したいと思っており、自分が父の世話を最期までするつもりでいる。私達姉妹はそれに出来る限り協力するよう努めることにした。私に出来る事は年に数回帰省し、その間私が父の世話をし、兄姉の介護負担を軽減することであると認識したため、遠距離介護を選択した。
![]() 年に5、6回の帰省。 介護保険を利用。民間のサービスは利用していない。週3回(1回2時間)ヘルパーさんの訪問で身体の清拭、食事の介助(ごく稀に)、話し相手をお願いしている。兄に急用ができた時は突然でもヘルパーさんが5、6時間来てくれる。今年7月に介護保険でベッドをレンタルした。
年に5、6回の帰省。 介護保険を利用。民間のサービスは利用していない。週3回(1回2時間)ヘルパーさんの訪問で身体の清拭、食事の介助(ごく稀に)、話し相手をお願いしている。兄に急用ができた時は突然でもヘルパーさんが5、6時間来てくれる。今年7月に介護保険でベッドをレンタルした。
![]() 遠く離れているため、介護について兄との意思疎通が上手くいかない。私は介護遠く離れているため、介護について兄との意思疎通が上手くいかない。私は介護保険を活用してできるだけ兄の負担が少なくなることを願っている。しかし姉と私のその願いを聞き入れようとはしない。 姉と私は、父が家族以外の人と接する機会が多く持てるようにまた、兄ができるだけスムーズに父の世話ができるようにと考え、2年前にやむなく介護保険を申請した。同意はしたものの兄は最小限の利用しか望まない。面倒なことも手伝って介護サービスを見直し、より良い形で活用しようといったことはしないのである。
ある時兄に所用ができ、2泊3日での外出が決まっていた。姉も私もその時期は都合がつかず留守番できないため、私はショートステイの利用を提案した。父にとっても違った環境は気分転換になって良いのではとも思ったからだ。姉が準備をし、施設から父が戻る日に私が実家へ行く事にすれば兄の手を煩わさずにすむ。環境の変化で父が動揺することがあっても一週間私がいれば何とか対応できるのではないか、と考えてのことだった。しかし姉がこの話をしたところ兄は所用を取り消しショートステイの話はボツになった。いつまで続くか分からない介護。今年7月風邪で入院して以来ほとんど寝たきり状態となった父を世話する兄の体を心配して、今後ショートステイを利用するには絶好のチャンスだと思い決めたことだが、受け入れられなかった。兄は「父の世話に限界を感じた時に考えるから大丈夫」と言うが、その時はボロボロになっているのではないかと心配である。
遠く離れているため、介護について兄との意思疎通が上手くいかない。私は介護遠く離れているため、介護について兄との意思疎通が上手くいかない。私は介護保険を活用してできるだけ兄の負担が少なくなることを願っている。しかし姉と私のその願いを聞き入れようとはしない。 姉と私は、父が家族以外の人と接する機会が多く持てるようにまた、兄ができるだけスムーズに父の世話ができるようにと考え、2年前にやむなく介護保険を申請した。同意はしたものの兄は最小限の利用しか望まない。面倒なことも手伝って介護サービスを見直し、より良い形で活用しようといったことはしないのである。
ある時兄に所用ができ、2泊3日での外出が決まっていた。姉も私もその時期は都合がつかず留守番できないため、私はショートステイの利用を提案した。父にとっても違った環境は気分転換になって良いのではとも思ったからだ。姉が準備をし、施設から父が戻る日に私が実家へ行く事にすれば兄の手を煩わさずにすむ。環境の変化で父が動揺することがあっても一週間私がいれば何とか対応できるのではないか、と考えてのことだった。しかし姉がこの話をしたところ兄は所用を取り消しショートステイの話はボツになった。いつまで続くか分からない介護。今年7月風邪で入院して以来ほとんど寝たきり状態となった父を世話する兄の体を心配して、今後ショートステイを利用するには絶好のチャンスだと思い決めたことだが、受け入れられなかった。兄は「父の世話に限界を感じた時に考えるから大丈夫」と言うが、その時はボロボロになっているのではないかと心配である。
![]() 昨年9月から父の認知症がひどくなり、兄が振り回されている時期があった。帰省してその状況を見た私は兄が過労で倒れるのではないかと心配になり、電話でケアマネジャーさんにサービス内容の変更について相談した。しかし「お兄さんは何も言わないのに、遠くにいる貴女の意見は受け入れ難い。それにお父さんのことを一番に考えなくてはいけない」との返答 。確かにそうなのかもしれない。遠方にいる者は、介護する者、される者の心配をしても肝心なところでは何もできず、現状を受け入れざるを得ないことを痛感した。
昨年9月から父の認知症がひどくなり、兄が振り回されている時期があった。帰省してその状況を見た私は兄が過労で倒れるのではないかと心配になり、電話でケアマネジャーさんにサービス内容の変更について相談した。しかし「お兄さんは何も言わないのに、遠くにいる貴女の意見は受け入れ難い。それにお父さんのことを一番に考えなくてはいけない」との返答 。確かにそうなのかもしれない。遠方にいる者は、介護する者、される者の心配をしても肝心なところでは何もできず、現状を受け入れざるを得ないことを痛感した。
(会報パオッコ3号より)
体験談:005
H・Tさん(東京都 50代男性)
![]() 鳥取県米子市。父83歳、母76歳、夫婦ふたりでの生活。父は要介護2、腰と膝を数回手術し、現在は家の中を歩くのがやっとの状態。腎臓と心臓も弱く、軽い脳梗塞の後遺症がある。母は心臓の病気で障害者登録をしている。50代に腰の骨を圧迫骨折、長時間台所に立つことや階段の上り下りはきつい。車で5分程度のところに姉が住んでいて、ときどき様子をみにいってくれている。
鳥取県米子市。父83歳、母76歳、夫婦ふたりでの生活。父は要介護2、腰と膝を数回手術し、現在は家の中を歩くのがやっとの状態。腎臓と心臓も弱く、軽い脳梗塞の後遺症がある。母は心臓の病気で障害者登録をしている。50代に腰の骨を圧迫骨折、長時間台所に立つことや階段の上り下りはきつい。車で5分程度のところに姉が住んでいて、ときどき様子をみにいってくれている。
![]() まず、両親は生来ほとんど米子以外で暮らしたことがなく、友人や親戚も米子近辺にしかいないため、米子を離れて暮らすことは不可能。したがって、東京へ呼び寄せるという選択はありえない。これは施設に入所した場合も同じ。一方、私の子どもたちのひとりは東京で就職、もうひとりは山梨の大学に在学中。子どもたちとのコミュニケーションを大切にしたいため、現在の自宅(持ち家=マンション)を離れたくない。仮にUターンしたとしてもローンを払い続けられるだけの収入を得られる見込みがなく、自分の家族の将来のあり方を考えるとUターンという選択はできない。また、マンションを売り払ってUターンするには、嫁姑の関係も1から築いていかなければならず、親世代と子世代互いのためにもよくないと考える。
まず、両親は生来ほとんど米子以外で暮らしたことがなく、友人や親戚も米子近辺にしかいないため、米子を離れて暮らすことは不可能。したがって、東京へ呼び寄せるという選択はありえない。これは施設に入所した場合も同じ。一方、私の子どもたちのひとりは東京で就職、もうひとりは山梨の大学に在学中。子どもたちとのコミュニケーションを大切にしたいため、現在の自宅(持ち家=マンション)を離れたくない。仮にUターンしたとしてもローンを払い続けられるだけの収入を得られる見込みがなく、自分の家族の将来のあり方を考えるとUターンという選択はできない。また、マンションを売り払ってUターンするには、嫁姑の関係も1から築いていかなければならず、親世代と子世代互いのためにもよくないと考える。
![]() 年に1回程度帰省。父が介護保険を使っている…デイサービス、設備のリース、介護タクシー。民間のサービスはほとんど利用していない。
年に1回程度帰省。父が介護保険を使っている…デイサービス、設備のリース、介護タクシー。民間のサービスはほとんど利用していない。
![]() 両親の近くにいる姉は仕事をもっていて、しょっちゅう様子をみにいけるわけではない。そのため両親との心のすれ違いも多く、そのたびに私が仲裁に入ることになるが、電話ではそれがかなり難しく、神経をすり減らすことになる。両親の身体的機能は十分とはいえないものの、ふたりで生活しているあいだは緊急時もどちらかが連絡できるため、今は四六時中心配するほどではない。しかし、どちらかのひとり暮らしとなると、安否の確認のための措置をいろいろ工夫しなければならないだろう。そのためにも、ヘルパーの導入や民生委員への相談など、今は絶対にいやだと拒否していることについて親を説得していかなければならない。そのための時間がとれないのが悩み。そのほかにも、施設に入ることになった場合、家の売却に伴って、仏壇の置き場をどうするか、墓の維持を誰にどのように任せていくのかなど、いろいろ悩ましい問題が残っている。
両親の近くにいる姉は仕事をもっていて、しょっちゅう様子をみにいけるわけではない。そのため両親との心のすれ違いも多く、そのたびに私が仲裁に入ることになるが、電話ではそれがかなり難しく、神経をすり減らすことになる。両親の身体的機能は十分とはいえないものの、ふたりで生活しているあいだは緊急時もどちらかが連絡できるため、今は四六時中心配するほどではない。しかし、どちらかのひとり暮らしとなると、安否の確認のための措置をいろいろ工夫しなければならないだろう。そのためにも、ヘルパーの導入や民生委員への相談など、今は絶対にいやだと拒否していることについて親を説得していかなければならない。そのための時間がとれないのが悩み。そのほかにも、施設に入ることになった場合、家の売却に伴って、仏壇の置き場をどうするか、墓の維持を誰にどのように任せていくのかなど、いろいろ悩ましい問題が残っている。
![]() 企業に就職すればほとんど都会にしか仕事がなくなり、大家族で暮らしていたときには当たり前だった親子の関係は引き裂かれる。やがて親が年老いて、親への感謝の気持ちをいちばんあらわしたいころには、都会に根づいた自分の家族の生活とどちらをとるか、二者択一の判断を迫られることになる。これは、核家族化を進行させた現代社会の大きな落ち度だと思う。親を介護するためのUターンをしない子どもたちは、親の暮らす地域の人から「親不孝者」と見られがち。それを情けなく思う娘や息子、あるいは「長男の嫁」の、板ばさみの心情を、生まれた地域でずっと暮らしてきた人たちにも、広く社会的にも理解してもらいたいと心から望む。
企業に就職すればほとんど都会にしか仕事がなくなり、大家族で暮らしていたときには当たり前だった親子の関係は引き裂かれる。やがて親が年老いて、親への感謝の気持ちをいちばんあらわしたいころには、都会に根づいた自分の家族の生活とどちらをとるか、二者択一の判断を迫られることになる。これは、核家族化を進行させた現代社会の大きな落ち度だと思う。親を介護するためのUターンをしない子どもたちは、親の暮らす地域の人から「親不孝者」と見られがち。それを情けなく思う娘や息子、あるいは「長男の嫁」の、板ばさみの心情を、生まれた地域でずっと暮らしてきた人たちにも、広く社会的にも理解してもらいたいと心から望む。
(会報パオッコ2号より)
体験談:004
M・Iさん(東京都 50代女性)
![]() 兵庫県神戸市。母82歳。要介護1で、ケアハウスに入居している。 1年半前に大腿骨を骨折したが、すっかり回復。しかし、足、腰、膝が全体に弱くなり、施設の中(慣れたところ)はスムーズに歩けるものの、外に出ると心もとない歩き方で、少し長く歩くと疲れてしまう。朝と夕の2回、施設の仲間と職員とでゆっくり散歩にいっているようだ。ケアハウスはとても居心地がいいらしく、気分よく暮らしている。明石に住む弟が、週1回日曜日に会いにいっている。
兵庫県神戸市。母82歳。要介護1で、ケアハウスに入居している。 1年半前に大腿骨を骨折したが、すっかり回復。しかし、足、腰、膝が全体に弱くなり、施設の中(慣れたところ)はスムーズに歩けるものの、外に出ると心もとない歩き方で、少し長く歩くと疲れてしまう。朝と夕の2回、施設の仲間と職員とでゆっくり散歩にいっているようだ。ケアハウスはとても居心地がいいらしく、気分よく暮らしている。明石に住む弟が、週1回日曜日に会いにいっている。
![]() ひとりでいるという不安が大きく、母の中には家にひとりで住むという選択はなかったようだ。生まれも育ちも神戸、そのうえ友だち、親戚、弟も神戸近郊に住んでいる母は神戸の施設に入居した。私の弟にもいろいろ事情があって母との同居は考えられず、母も娘の私と住みたいと言うので、母を呼び寄せられるように東京の我が家をリフォームして待っていたが、いざとなると神戸を離れる決心がつかない様子。今年の4~5月にお試しのようなかたちで東京に呼んだが、やはり神戸がいいのか帰ってしまった。今は落ち着いた様子でホーム暮らし。子どもたちも東京に定住した今、私たち一家がUターンするという考えはないので、遠距離介護を続けることになった。
ひとりでいるという不安が大きく、母の中には家にひとりで住むという選択はなかったようだ。生まれも育ちも神戸、そのうえ友だち、親戚、弟も神戸近郊に住んでいる母は神戸の施設に入居した。私の弟にもいろいろ事情があって母との同居は考えられず、母も娘の私と住みたいと言うので、母を呼び寄せられるように東京の我が家をリフォームして待っていたが、いざとなると神戸を離れる決心がつかない様子。今年の4~5月にお試しのようなかたちで東京に呼んだが、やはり神戸がいいのか帰ってしまった。今は落ち着いた様子でホーム暮らし。子どもたちも東京に定住した今、私たち一家がUターンするという考えはないので、遠距離介護を続けることになった。
![]() 月に1~2回帰省(2~3週間ごとに4~5日)。ケアハウス入居中なので介護保険を使っている。東京の我が家に来たときは、介護保険でベッドと車椅子をレンタル。施設に入っていても外泊中ということで介護保険が利用できるそうで、とても助かった。実家は、私が帰省しないあいだ閉め切りになり、用心が悪いので、民間(セコム)の警備サービスを利用している。
月に1~2回帰省(2~3週間ごとに4~5日)。ケアハウス入居中なので介護保険を使っている。東京の我が家に来たときは、介護保険でベッドと車椅子をレンタル。施設に入っていても外泊中ということで介護保険が利用できるそうで、とても助かった。実家は、私が帰省しないあいだ閉め切りになり、用心が悪いので、民間(セコム)の警備サービスを利用している。
![]() 行ったきり介護も含め5年近く遠距離介護を続けていると、もう生活の一部のようになり、「次は○○日から神戸ね」などと、家族、友だちともじょうずに予定を組むようになってきた。すっかり自然体の遠距離介護といったところ。でも、このごろ夫は疲れぎみ、娘は妊娠で具合が悪く家族一同でころがりこんでくる、孫のめんどうは一日中みなくてはいけない……母は2~3週間で私がまた来ると思っているので、「次はいつ?」ときいては予定がずれると不機嫌になる……両方のバランスをとるのが難しいなと思うこともある。人の住んでいない実家は、玄関を開けると(特に夏)モワーとしたムッとするような空気と虫、草むしりをして帰ったはずの庭にいっぱいの草。この実家の草むしりや掃除(網戸洗いやガラス拭き)が頭の痛い問題のひとつ。母が病気をしたら今の施設を出なくてはいけないと心配だが、あまり心配を先取りせず、日々楽しく暮らしてほしい。そのときそのとき、いちばんいい選択をしたいと思っている。
行ったきり介護も含め5年近く遠距離介護を続けていると、もう生活の一部のようになり、「次は○○日から神戸ね」などと、家族、友だちともじょうずに予定を組むようになってきた。すっかり自然体の遠距離介護といったところ。でも、このごろ夫は疲れぎみ、娘は妊娠で具合が悪く家族一同でころがりこんでくる、孫のめんどうは一日中みなくてはいけない……母は2~3週間で私がまた来ると思っているので、「次はいつ?」ときいては予定がずれると不機嫌になる……両方のバランスをとるのが難しいなと思うこともある。人の住んでいない実家は、玄関を開けると(特に夏)モワーとしたムッとするような空気と虫、草むしりをして帰ったはずの庭にいっぱいの草。この実家の草むしりや掃除(網戸洗いやガラス拭き)が頭の痛い問題のひとつ。母が病気をしたら今の施設を出なくてはいけないと心配だが、あまり心配を先取りせず、日々楽しく暮らしてほしい。そのときそのとき、いちばんいい選択をしたいと思っている。
![]() 「娘と暮らしたい」と言うので東京に「おいでよ」と連れてきたのに、「施設を追い出されたのでは?」、「もう神戸へ帰れないのでは?」、あげくに「神戸で生まれたのに、神戸で死ねないのね!」と不安、妄想がわいてきて、母は精神不安定になってしまった。家族じゅうで歓迎すればするほど「神戸に帰れないんだ」と思い込んでいく様子に驚いてしまった。してほしいことをしたつもりなのに、うまくいかない、というか、思ってもみない結果になるとは……。何ごともやってみないとわからない、ひとりひとり違うんだということがよくわかり、勉強になったできごとだった。
「娘と暮らしたい」と言うので東京に「おいでよ」と連れてきたのに、「施設を追い出されたのでは?」、「もう神戸へ帰れないのでは?」、あげくに「神戸で生まれたのに、神戸で死ねないのね!」と不安、妄想がわいてきて、母は精神不安定になってしまった。家族じゅうで歓迎すればするほど「神戸に帰れないんだ」と思い込んでいく様子に驚いてしまった。してほしいことをしたつもりなのに、うまくいかない、というか、思ってもみない結果になるとは……。何ごともやってみないとわからない、ひとりひとり違うんだということがよくわかり、勉強になったできごとだった。
(会報パオッコ2号より)
体験談:003
K・Oさん(東京都 50代女性)
![]() 兵庫県神戸市。母82歳。要介護1で、ケアハウスに入居している。 島根県西部。母84歳、ひとり暮らし。4年前に父が他界し、母のひとり暮らしとなった。子どもは私ひとりで、母にも兄弟姉妹がいないために近所には近しい親戚はいない。ただし、住んでいるのが小さな漁村なので、昔からの親戚、知人と親しいつきあい方をして毎日過ごしている。要介護1で、近ごろではベッドに寝ていることが多くなった。
兵庫県神戸市。母82歳。要介護1で、ケアハウスに入居している。 島根県西部。母84歳、ひとり暮らし。4年前に父が他界し、母のひとり暮らしとなった。子どもは私ひとりで、母にも兄弟姉妹がいないために近所には近しい親戚はいない。ただし、住んでいるのが小さな漁村なので、昔からの親戚、知人と親しいつきあい方をして毎日過ごしている。要介護1で、近ごろではベッドに寝ていることが多くなった。
![]() 母にとっては今の家が自分の生まれた家であり、ひとりになっても東京には行かないと最初から言っていた。私自身も母を呼び寄せて東京で生活させようとは思っていなかった。両親が夫婦ふたり暮らしだったころは年に1度か2度の帰省ですませていたが、母ひとりになると淋しい淋しいと口にするようになり、父の死後はたびたび帰省することを選んでいる。私が帰京する際は、今度はいつ来るのかときき、カレンダーに印をつけて心待ちにしている様子。
母にとっては今の家が自分の生まれた家であり、ひとりになっても東京には行かないと最初から言っていた。私自身も母を呼び寄せて東京で生活させようとは思っていなかった。両親が夫婦ふたり暮らしだったころは年に1度か2度の帰省ですませていたが、母ひとりになると淋しい淋しいと口にするようになり、父の死後はたびたび帰省することを選んでいる。私が帰京する際は、今度はいつ来るのかときき、カレンダーに印をつけて心待ちにしている様子。
![]() 私が2カ月に1度帰省して母の様子をみている。ベッドにいる時間が長くなったので、介護保険でデイサービスを月2回利用している。民間のサービスでは、NPO介護事業所の安否確認電話を利用。月~金曜日の毎朝、母のところに安否を確認する電話をかけてもらっている。また、月に2回、近所の友人と一緒に自宅で、有償ボランティアに絵手紙を習っている。80歳過ぎての手習いで決してじょうずとは言えないが、作品を私に送ることが、今のところ最大の生きがいと感じられるようだ。
私が2カ月に1度帰省して母の様子をみている。ベッドにいる時間が長くなったので、介護保険でデイサービスを月2回利用している。民間のサービスでは、NPO介護事業所の安否確認電話を利用。月~金曜日の毎朝、母のところに安否を確認する電話をかけてもらっている。また、月に2回、近所の友人と一緒に自宅で、有償ボランティアに絵手紙を習っている。80歳過ぎての手習いで決してじょうずとは言えないが、作品を私に送ることが、今のところ最大の生きがいと感じられるようだ。
![]() 緊急の場合、誰に頼めばよいか、いつも不安に思っている。幸いにも今の介護事務所では、介護保険以外にも有償でサービスを使うことができる。でも、夜間や休日のことを思うと、やはり心配。母が暮らすのは昔から閉鎖的な地域で、3軒に1軒が老夫婦か独居家庭という状態であるにもかかわらず、介護保険の導入にも人の目を気にしてなかなかうまくことを運べなかった。
緊急の場合、誰に頼めばよいか、いつも不安に思っている。幸いにも今の介護事務所では、介護保険以外にも有償でサービスを使うことができる。でも、夜間や休日のことを思うと、やはり心配。母が暮らすのは昔から閉鎖的な地域で、3軒に1軒が老夫婦か独居家庭という状態であるにもかかわらず、介護保険の導入にも人の目を気にしてなかなかうまくことを運べなかった。
![]() 子との同居が望めないことが多くなった社会状況のなかで、今、老親が自分の望むところで生活したいと思えば、多くの人の手助けが必要になってくる。社会が、介護保険の介護だけに目を向けるのではなく、ちょっとした手助けで安心して生活できるようなサービスの導入にも力を入れてほしいと思っている。
子との同居が望めないことが多くなった社会状況のなかで、今、老親が自分の望むところで生活したいと思えば、多くの人の手助けが必要になってくる。社会が、介護保険の介護だけに目を向けるのではなく、ちょっとした手助けで安心して生活できるようなサービスの導入にも力を入れてほしいと思っている。
(会報パオッコ2号より)
体験談:002
H・Iさん(東京都 40代女性)
![]() 北海道。父83歳、母83歳。父は3年前、母は今年、それぞれ別の施設に入居。父は5年前にアルツハイマーと診断され服薬治療開始、グループホームでの生活が落ち着き、要介護1の状態を保っている。淋しがることも多いが、訪ねていくと男性入居者はひとりきりであるにもかかわらずほかの入居者との交流もある様子。父の具合が悪くなったころちょうど腕を骨折したり、いろいろ負担を抱えた母は、高血圧、脳梗塞の後遺症も重なって一昨年要支援、昨年要介護1から、歩けないと言って入院したあいだに要介護3にまで自立度が落ちてしまった。高齢者用マンション入居の話が直前になってご破算になり、急遽私が奔走したあげく父のいるところに隣接した施設に入所。ときどき妄想のような症状があらわれることもある。様子を知らせてくれたり頼みごとのできる、母のきょうだいや親戚が近くにいる。ただし、私はひとりっ子。
北海道。父83歳、母83歳。父は3年前、母は今年、それぞれ別の施設に入居。父は5年前にアルツハイマーと診断され服薬治療開始、グループホームでの生活が落ち着き、要介護1の状態を保っている。淋しがることも多いが、訪ねていくと男性入居者はひとりきりであるにもかかわらずほかの入居者との交流もある様子。父の具合が悪くなったころちょうど腕を骨折したり、いろいろ負担を抱えた母は、高血圧、脳梗塞の後遺症も重なって一昨年要支援、昨年要介護1から、歩けないと言って入院したあいだに要介護3にまで自立度が落ちてしまった。高齢者用マンション入居の話が直前になってご破算になり、急遽私が奔走したあげく父のいるところに隣接した施設に入所。ときどき妄想のような症状があらわれることもある。様子を知らせてくれたり頼みごとのできる、母のきょうだいや親戚が近くにいる。ただし、私はひとりっ子。
![]() 北海道のひとと結婚し、もともと親のもとを遠く離れたつもりではなかったのに、夫の仕事の関係でいつのまにか転勤族に。3人の子どもたちも小さいころから転校の連続、学年途中で転校したため修学旅行を経験しそこねたこともあるくらい。選択もなにも、この先どこに引っ越すことになるのかもわからない。両親は私のことを「嫁に出した」つもりでいるし、例えばいちばんこみいったかたちだと、私が親と同居して介護、夫は単身赴任、子どもは下宿……そんなことは精神的にも経済的にもとても無理。
北海道のひとと結婚し、もともと親のもとを遠く離れたつもりではなかったのに、夫の仕事の関係でいつのまにか転勤族に。3人の子どもたちも小さいころから転校の連続、学年途中で転校したため修学旅行を経験しそこねたこともあるくらい。選択もなにも、この先どこに引っ越すことになるのかもわからない。両親は私のことを「嫁に出した」つもりでいるし、例えばいちばんこみいったかたちだと、私が親と同居して介護、夫は単身赴任、子どもは下宿……そんなことは精神的にも経済的にもとても無理。
![]() 6年くらい前までは家族で年に2回帰省していた。父が不調になってからは、前売り割引の航空券で私が毎月通うようになり、父のグループホーム入所で母がひとり暮らしになった3年前からは、母の様子に合わせてキャンセルしては予約し直す無駄が多くなったため、JAL時刻表で見つけた介護帰省割引を利用、毎月1週間ほど帰省している。当初は、脳神経外科で出される薬を父がきちんと飲むように、私が毎回箱に整理しておいたり、ひとりで必死だった。いいケアマネージャーと知り合って、父の介護保険申請を頼み、その後も引き続き母のときにもお世話になった。介護保険サービスの訪問看護で薬の管理もしてもらえるようになり、母の負担を減らせるようにショートステイも利用。グループホームもケアマネからの情報で見学に行った。ひとり暮らしになった母を「温泉のつもりで行っておいでよ」と説き伏せて、入浴と昼食にデイサービスを利用。ほかに、冬の通院など心配なので、週1回ヘルパーを頼んだ。
今はそれぞれの施設にひんぱんに電話して親と話をするようにし、月1回訪ねたときには、勝手には外出できない両親を外へ連れ出したりも。年に1度は両親を脳神経外科に連れていく。また、住む者のいなくなった実家の管理にも気が抜けない。北海道の住宅では冬場に水道管が破裂する危険があるので、業者に問い合わせて水抜きは自分でしたが、雪かきはシルバー人材センターに依頼した。
6年くらい前までは家族で年に2回帰省していた。父が不調になってからは、前売り割引の航空券で私が毎月通うようになり、父のグループホーム入所で母がひとり暮らしになった3年前からは、母の様子に合わせてキャンセルしては予約し直す無駄が多くなったため、JAL時刻表で見つけた介護帰省割引を利用、毎月1週間ほど帰省している。当初は、脳神経外科で出される薬を父がきちんと飲むように、私が毎回箱に整理しておいたり、ひとりで必死だった。いいケアマネージャーと知り合って、父の介護保険申請を頼み、その後も引き続き母のときにもお世話になった。介護保険サービスの訪問看護で薬の管理もしてもらえるようになり、母の負担を減らせるようにショートステイも利用。グループホームもケアマネからの情報で見学に行った。ひとり暮らしになった母を「温泉のつもりで行っておいでよ」と説き伏せて、入浴と昼食にデイサービスを利用。ほかに、冬の通院など心配なので、週1回ヘルパーを頼んだ。
今はそれぞれの施設にひんぱんに電話して親と話をするようにし、月1回訪ねたときには、勝手には外出できない両親を外へ連れ出したりも。年に1度は両親を脳神経外科に連れていく。また、住む者のいなくなった実家の管理にも気が抜けない。北海道の住宅では冬場に水道管が破裂する危険があるので、業者に問い合わせて水抜きは自分でしたが、雪かきはシルバー人材センターに依頼した。
![]() 実家は、私が帰省の拠点に使ってはいるものの、トイレだけしか水が使えないし、親が家に帰りたがっても、施設から実家への外泊もままならない。最近、夫が定年退職するのはいつごろになるのかと、父が私に意味深な質問をしてきたのが気になる。また、母の自立度が急激に落ちたことで、みすみす入院させてしまった罪悪感をどうしてもぬぐえない。親戚には私ががんばっていることを評価されているようだが、「あなたひとりの肩にかかっている」というふうな言われ方はプレッシャーでもある。
実家は、私が帰省の拠点に使ってはいるものの、トイレだけしか水が使えないし、親が家に帰りたがっても、施設から実家への外泊もままならない。最近、夫が定年退職するのはいつごろになるのかと、父が私に意味深な質問をしてきたのが気になる。また、母の自立度が急激に落ちたことで、みすみす入院させてしまった罪悪感をどうしてもぬぐえない。親戚には私ががんばっていることを評価されているようだが、「あなたひとりの肩にかかっている」というふうな言われ方はプレッシャーでもある。
![]() 転勤続きでかつて私が体調をくずしたころから、子どもたちもずっと家事その他の負担を分担してきてくれたと思う。また、介護帰省のついでに高齢者用マンションでひとり暮らしをしている夫の母の様子もみてほしいというのを、とても余裕がないので断ってきたが、夫も理解してくれたようだ。とにかく、なるようになる、考えてもしかたがないと思っている。今は、空港と実家のあいだを走る列車の中で、交通機関のプリペイドカード類の北海道用セットと東京用セットをバッグに入れ替えるとともに、気持ちを切り替える。一面では、親のケアをきっかけに、自分のためにもという気持ちで、自立支援体操やささえあいサービスの講習を受けたり、基礎介護講座を受講したりもしている。
転勤続きでかつて私が体調をくずしたころから、子どもたちもずっと家事その他の負担を分担してきてくれたと思う。また、介護帰省のついでに高齢者用マンションでひとり暮らしをしている夫の母の様子もみてほしいというのを、とても余裕がないので断ってきたが、夫も理解してくれたようだ。とにかく、なるようになる、考えてもしかたがないと思っている。今は、空港と実家のあいだを走る列車の中で、交通機関のプリペイドカード類の北海道用セットと東京用セットをバッグに入れ替えるとともに、気持ちを切り替える。一面では、親のケアをきっかけに、自分のためにもという気持ちで、自立支援体操やささえあいサービスの講習を受けたり、基礎介護講座を受講したりもしている。
(会報パオッコ2号より)
体験談:001
M・Nさん(東京都 40代女性)
![]() 兵庫県神戸市。母82歳。要介護1で、ケアハウスに入居している。 島根県西部。母84歳、ひとり暮らし。4年前に父が他界し、母のひとり暮らしとなった。子どもは私ひとりで、母にも兄弟姉妹がいないために近所には近しい親戚はいない。ただし、住んでいるのが小さな漁村なので、昔からの親戚、知人と親しいつきあい方をして毎日過ごしている。要介護1で、近ごろではベッドに寝ていることが多くなった。
兵庫県神戸市。母82歳。要介護1で、ケアハウスに入居している。 島根県西部。母84歳、ひとり暮らし。4年前に父が他界し、母のひとり暮らしとなった。子どもは私ひとりで、母にも兄弟姉妹がいないために近所には近しい親戚はいない。ただし、住んでいるのが小さな漁村なので、昔からの親戚、知人と親しいつきあい方をして毎日過ごしている。要介護1で、近ごろではベッドに寝ていることが多くなった。
![]() 父は自分が「本家の長男」であるという意識ぬぐいがたく、家と墓から離れることなど考えられない。近隣から嫁いできた母も、地元に張った根は今さら抜きがたいものがある。末っ子長男である弟がいずれ家を継ぐことを期待されていたが、結婚、就職した土地に数年前家を建て、弟一家はかろうじて年に1度帰省するかどうかといったところ。私と妹のUターンは親にとって想定外だろうと、選択というよりはなりゆきで遠距離でのケアを覚悟するに至った。ただし、20代で短期Uターンの経験もある私は子どものいない夫婦ふたり自由業という生活、子どもたちが独立した後の生活は未定(笑)と言う妹とともに、Uターンの選択肢を捨ててはいない。
父は自分が「本家の長男」であるという意識ぬぐいがたく、家と墓から離れることなど考えられない。近隣から嫁いできた母も、地元に張った根は今さら抜きがたいものがある。末っ子長男である弟がいずれ家を継ぐことを期待されていたが、結婚、就職した土地に数年前家を建て、弟一家はかろうじて年に1度帰省するかどうかといったところ。私と妹のUターンは親にとって想定外だろうと、選択というよりはなりゆきで遠距離でのケアを覚悟するに至った。ただし、20代で短期Uターンの経験もある私は子どものいない夫婦ふたり自由業という生活、子どもたちが独立した後の生活は未定(笑)と言う妹とともに、Uターンの選択肢を捨ててはいない。
![]() 年に2回プラスアルファの帰省。介護保険、民間サービスとも、現状では何も利用していない。何かあったとき当面の費用に困らないよう、きょうだいで郵便貯金の定額積み立てをしている。月に2、3回は親に電話するように心がけ、気づきをメモして「経過記録」としている。昨年、私の副回線として契約した携帯電話を母に渡してからはちょくちょくメールをやりとりするようになって、ささいな連絡もしやすくなった。エンディングノートを試しに2種類購入したがどうしたものかと迷っていたが、パオッコのセミナーで石川由紀さんのお話を聞いてなるほどと思い、自分で親のことを記録するのに活用しようと考えているところ。
年に2回プラスアルファの帰省。介護保険、民間サービスとも、現状では何も利用していない。何かあったとき当面の費用に困らないよう、きょうだいで郵便貯金の定額積み立てをしている。月に2、3回は親に電話するように心がけ、気づきをメモして「経過記録」としている。昨年、私の副回線として契約した携帯電話を母に渡してからはちょくちょくメールをやりとりするようになって、ささいな連絡もしやすくなった。エンディングノートを試しに2種類購入したがどうしたものかと迷っていたが、パオッコのセミナーで石川由紀さんのお話を聞いてなるほどと思い、自分で親のことを記録するのに活用しようと考えているところ。
![]() どうみても長男一家との同居は非現実的な現状で、親の真意をはかりかねている。親の身近では血縁も地縁も濃いことを心強く思う一方、だからこそよけいに子どもがみな遠くにいることで肩身が狭いのではないかという妄想につきまとわれる。淋しがりやでコミュニケーション下手な父とはどうやら私がいちばん無難につきあえるらしいので、父親との話題をつなごうと努めた結果(?)すっかりオヤジくさくなってしまった。今はぬるま湯状態だが、自分の健康を過信ぎみで負けず嫌いの母が、健康診断などに手を抜いているのがかえってシンパイ。
どうみても長男一家との同居は非現実的な現状で、親の真意をはかりかねている。親の身近では血縁も地縁も濃いことを心強く思う一方、だからこそよけいに子どもがみな遠くにいることで肩身が狭いのではないかという妄想につきまとわれる。淋しがりやでコミュニケーション下手な父とはどうやら私がいちばん無難につきあえるらしいので、父親との話題をつなごうと努めた結果(?)すっかりオヤジくさくなってしまった。今はぬるま湯状態だが、自分の健康を過信ぎみで負けず嫌いの母が、健康診断などに手を抜いているのがかえってシンパイ。
![]() 親や故郷に愛情、愛着がないわけじゃないけれど、もしずっと同居していたらどうだっただろうかと想像してみることがある。親とは理解し合えないことも多く、険悪な親子関係になっていたかもしれない。例えば、遠く離れているからこそ今の私は父と話がはずむよう努力もしているが、一緒に暮らしていたら口もききたくなくなっていたかも……。「親不孝者の言い訳」かもしれないが、離れて暮らすことには距離感ではぐくまれる何かもあって、悪いことばかりでもないのではないか。
親や故郷に愛情、愛着がないわけじゃないけれど、もしずっと同居していたらどうだっただろうかと想像してみることがある。親とは理解し合えないことも多く、険悪な親子関係になっていたかもしれない。例えば、遠く離れているからこそ今の私は父と話がはずむよう努力もしているが、一緒に暮らしていたら口もききたくなくなっていたかも……。「親不孝者の言い訳」かもしれないが、離れて暮らすことには距離感ではぐくまれる何かもあって、悪いことばかりでもないのではないか。
(会報パオッコ2号より)